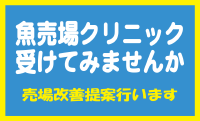�悤���� FISH FOOD TIMES ��
�N���R���T���^���g�������X�V���鋛�̒m���ƋZ�p�̃z�[���y�[�W
����30�N 5�����@��173


�q���_�C�p����h�g
�}�`�͉���̑�\�I�ȋ��̈��
�q���_�C�Ƃ�����ʖ��̂́A����n���ŃN���L���}�`�A���������ł̓C�i�S�A���}�������̓I�S�A���䓇�ł̓R�}�X�Ȃǂ̖��̂ŌĂ�Ă���A��r�I�g�����C�ɐ������Ă������n�̔��g���ł���B

�q���_�C�i�N���L���}�`�j
�X�Y�L�n�X�Y�L���ڃt�G�_�C�ȃq���_�C���q���_�C�ɂƂĂ��ǂ������I�I�q���_�C�Ƃ����������邪�A����ŃN���L���}�`�ƌĂ��q���_�C�Ƃ悭��r����鋛�́A�A�I�_�C�i�t�G�_�C�ȃA�I�_�C���A����ł̕ʖ��̓V�`���[�}�`�A�������ł̓z�^�j�ł���A����ł̓N���L���}�`���V�`���[�}�`���A����Ƃ��A�J�}�`�i�t�G�_�C�ȃn�}�_�C���j���A�ƕ��я̂����}�`�̖��������鋛�ł���B
 �@�@
�@�@
�n�}�_�C�i�A�J�}�`�j�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�A�I�_�C�i�V�`���[�}�`�j
����̎s��Ŏ������鉿�i�̓A�J�}�`�A�V�`���[�}�`�A�N���L���}�`�̏��ō����̂����ʂł���A���l�Ƃ��Ă̓N���L���}�`����ԒႢ�ʒu�Â��ɂȂ��Ă���B���̗��R�𐄑�����ƁA�A�J�}�`�i�n�}�_�C�j�̓A�J�W���i�X�W�A���j�A�}�N�u�i�V���N���x���j�Ƌ��ɉ���3�卂�����̈�ł���A���̐Ԃ��F�̑��݊��������]������A�V�`���[�}�`�i�A�I�_�C�j�͓V�R�̔��g���炵���������������T�^�̋��ł���A�N���L���}�`�ɔ�ׂ�Ƒ�����������Ă���_���]������Ă��邩�炾�낤�B
�q���_�C�i�N���L���}�`�j�̎Y��������5�`7���ł���A2�ɂȂ��85�������n����Ƃ̌������ʂ����\����Ă���A���n�T�C�Y�ɒB����܂ł̊��Ԃ̓V�`���[�}�`�A�A�J�}�`�����Z�����߁A���̐������x�̑����䂦�ɉ��ꌧ�ł�2011�N�x���l�ʂ�139t�Ƒ���2������������A�܂����̂����܂�傫���Ȃ�Ȃ��̂�1��������̉��i����߂ōw�����₷���A�}�`�ƌĂ�鋛�̒��ł͈�ԑ�O�I�Ȉʒu�Â��ɂ���B
���̃A��������������������
����ł̓N���L���}�`�Ȃǂ̔��g�������摜�̂悤�ȁu���c���i���`�j�v�ɂ��ĐH�ׂ鎖�������B����͏����Ȃ��o�ł͂Ȃ����̂悤�ȑ傫���̋��R�̏`���ɂ��т�Ђ������t���ƁA���X�`�����C���f�B�b�V���ɂȂ�H����������B�����Đ̂Ȃ���̋��`�́A�����狛������Đg�������܂Ŏύ��ނ��ƂŁA��������|���������o���Ă���B
 �@
�@
�@�@�@�@�}�`�̋��`�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���`�炰����Ɏc�������̍�
���̂��c���̍ޗ��Ƃ��ĉ���̐l�B�ɑI��邱�Ƃ������̂̓N���L���}�`�ł���A�Ⴆ�Ζ{�y�̋��̐H�ו����悭�m��Ȃ��l�B�������⒆���ȂǕs�v�Ȃ��̂Ƃ��Čh������̂Ƃ͈���āA�t�ɉ���̋�����ł̔��g���̐ؐg��̔����鎞�́A���摜�̂悤�ɒ����⓪���������܂܂̏��i�̕�������̐l�ɂ͊���B
 �@�@
�@�@
�q���_�C�i�N���L���}�`�j�ؐg
����ł͋����������Ă��������̂Ă��ɐؐg�ƈꏏ�ɔ̔����邾���łȂ��A���̂��傫�ȋ��œ��������̂܂ܐؐg�ƈꏏ�ɓ���鎖���o���Ȃ��ꍇ���A�S�Ă̕��ʂ����������ăA���Ƃ��Ĕ̔����邪�A���̃A����ϋɓI�Ɋ��p����H����������̂ŁA�{�y�Ƃ͔�ׂ��̂ɂȂ�Ȃ��قǃA�����ǂ������B�Ⴆ�Ή���̂���X�[�p�[�ł́A�{�B���̐��Y��ЂȂǂ��^��̃u���t�B����J���p�`�t�B�������H����ۂɏo�Ă��铪�����킴�킴�ʂɎd����A�X�ő�ʂɔ̔����Ă����Ђ�����قǗǂ������̂ł���B
����̐H�����͓ؓ��𒆐S�Ƃ��Đ��藧���Ă��邱�Ƃ͔F�߂�Ƃ��Ă��A���̂����ۂ��ŋ��͓��⍜�����p���Ĕ��������������o�����ȐH�ו������t���Ă���̂��B���̂��Ƃ͖{�y�ɂ����鋛�ւ̖��S�Ɩ��m�ɋN�����鋛���ꌻ�ۂƔ�r����ƂȂ��Ȃ��D�܂������ۂł���A���ꂱ���{���̋��̔��������H�ו������Ă���Ƃ�������̂ł���B
�{��������������H�ׂ�Ƃ͂ǂ��������ƂȂ̂��A�ߋ���FISH FOOD TIMES ����27�N 4���� No.136�̂Ȃ��ŁA�M�҂͈ȉ��̂悤�ɋL���Ă����B
| FISH FOOD TIMES ����27�N 4���� No.136 ����A���͂̈ꕔ�� |
|---|
������������H�ׂ�ɂ́u���̍�����������悤�ȐH�ו��v�ւƓ�����̂ł͂Ȃ��A���̃A���̖��X�`�̂悤�Ɂu������o��|���������������v�����̕��Ɍ��������Ƃ��d�v�Ȃ̂ł���B���������̓��{�ɂ����ẮA���́u�|���v�Ƃ������Ƃ���������Ɨ�������Ă��Ȃ����Ƃ���A���������u�t�@�[�X�g�t�B�b�V���v�ȂǂƏ̂����A�H��Ő��Y���ꂽ���ՂŊȕւȏo���������i�ɐU��������ւƁA���{�̏���҂͌����킳��Ă���̂ł͂Ȃ����Ǝv�����̂�����B ���������u�|���v�Ƃ͉�����H�@�Q�l������R�����Ă݂�ƁE�E�E ����100�N�ȏ���O�ƂȂ�1908�N�ɁA�����鍑��w�����̒r�c�e�c�͍��z�o�`�̂��������̐��̂̓O���^�~���_�ł��邱�Ƃ����A�Ö��E�����E�_���E�ꖡ��4�̊�{���ł͐����ł��Ȃ����̖����u5�߂̊�{���v�Ƃ��āu�|���v�Ɩ������A���̃O���^�~���_���听���Ƃ��钲�����̐������@�ł̓������擾���A1909�N5���ɂ͎|���̒������ł���u���̑f�v����ؐ��i���̖��̑f������Ёj���甭�����ꂽ�B �����ł͉p��ɂ��́u�|���v��\�����t���Ȃ����߁A���ۓI�Ɋw�p�p��Ƃ��āuumami�v���g����悤�ɂȂ��Ă��邯��ǂ��A�����1980�N��ɂȂ��āu��Ɏ|���������������g�D������v���Ƃ��킩��A����Ɓu��5�̖��o�v�Ƃ��Đ��E�I�ɔF�߂���悤�ɂȂ������̂ŁA�|������������Ă����80�N���̒����ԁA���Ă̌����҂����́u�|���v�Ƃ����̂�4�̊�{�̖��o�̒��a�Ƃ��ĕ\��銴�o�ł����Ċ�{�̖��o�ł͂Ȃ��Ƃ��Ă����̂������B ���{�����ɂ����Ă͍��z�ŏo�`���Ƃ�����ɃJ�c�I�߂ŏo�`���Ƃ邪�A����͍��z�̃A�~�m�_�n�O���^�~���_�ƃJ�c�I�߂̊j�_�n�C�m�V���_�Ƃ����킹��ƁA���ꂼ�ꂪ�P�Ƃ̎������͂邩�ɋ����|����������悤�ɂȂ�Ƃ��������l�̌o���l���炫�Ă���̂ł���B �܂�C�m�V���_���L�x�ȋ��ƃO���^�~���_�𑽂��܂ލ��z��ő��̃O�A�j���_�Ȃǂ̐A�����H�i�����킹�ė�������Ǝ|�������ɋ��܂邱�ƂɂȂ�A�|���Ƃ����̂͑��̊�{���ɔ�ׂ�Ɩ������₩�ŁA�����������㖡�������̂������ƂȂ��Ă���B ���{�l���̂��疈���H�ׂĂ������X�`�Ƃ����̂́A�������̃C�m�V���_���L�x�ȃC���R�ƐA�����̃O���^�~���_�������Ղ�܂܂�Ă��閡�X�����R��̂ƂȂ��āA���̔������������o���Ă���̂ł���B�����̖��X�`�̒��ŃC���R���\�ɏo�Ă��Ȃ��B�ꂽ���Ƃ���Ȃ�A���̃A���̓C���R�Ƃ͋t�Ɂu�\�ɏo�Ă�������v�ƂȂ��Ă���̂��Ⴄ�Ƃ���ł���A�������̃C�m�V���_���L�x�ȃA���ƐA�����̖��X�̃O���^�~���_����]�t�]�����`�ƂȂ��Ă��邾���Ȃ̂��B ���X�`�̔������������o�I�ɗ������邽�߂Ɉ�Ԏ����葁�����@�́A�o�`�̎|���Ƃ��������̃x�[�X�ƂȂ��Ă��Ȃ����Ă̍��ւP�T�Ԉȏ㗷�s���A���̊Ԃ����������X�`�Ȃǂ̓��{�H��H�ׂ��A�A�����������̎���ł����ʂ�̖��X�`������ł݂邱�Ƃ��B��̏�Ŗ������݂��߂�悤�ɂ��Ȃ��疡�X�`������A���Ԃ�u���X�`���Ă���Ȃɔ������������̂��E�E�E���܂��I�v�Ɗ�������͂��ł���B ���������u���܂��I�v�ƌ��킹�邽�߂ɂ́A�������|�����������Ɉ����o���Ă�邱�Ƃ��K�v�ł���A���̂��߂ɂ͋��̂��Ƃ�ǂ��m�炸�ʓ|�Ȃ��Ƃ���肽����Ȃ�����҂̃j�[�Y�Ɍ}�����邱�Ƃ�����l����̂ł͂Ȃ��A�{���ɋ�����������H�ׂ�ɂ͂ǂ�����Ηǂ������A����葤������҂ɋ����Ă����邱�Ƃ��d�v�Ȃ��Ƃł͂Ȃ����Ǝv���B �t�@�[�X�g�t�B�b�V���ȂǂƂ����u����҂̋�����v�͓��X�̗�����S����w�Ȃǂ�ӑĂɂ��邾���ł���A���̖{���̖���m�邱�Ƃɂ͂Ȃ����Ă����Ȃ��Ǝv���A���̂悤�ȁu���H���y�ւ̖�D��v�Ƃ����̂́A���ʂƂ��Đ�X�̋��̏���A�b�v�ɂ͌��т��Ȃ��̂ł͂Ȃ����ƍl����B ����ɋ���̔����锄��葤�ɂ��Ă��A���̐ؐg��100�~�Ȃǂ̈������i�Ŕ���悤�Ȃ��Ƃɓ����g���̂ł͂Ȃ��A���̓��ɂ����p���l�����邱�Ƃ����q�l�ɒm�炵�߂邽�߂ɂ͂ǂ�����Ηǂ����A�Ƃ��������Ƃɂ������g���Ăق������̂ł���B��Ɉ��肵��������ւ鋛�̔ɐ��X�Ƃ����̂́A���̒��̌i�C���ǂ��Ȃ낤�Ƃ��ڐ�̈����ňꎞ�I�ȖA����������悤�Ȃ��Ƃ����A�����I�Ɉ��肵������������炵�Ă����ڋq��͂ނ��߂ɁA���������͍����Ă��i���̍������i��n���ɒ���u�{���u���̏����v���R�c�R�c�Ƒ����Ă���Ƃ��낪�����悤���B�u�{���u���v�Ƃ͌����č����Ƃ������t�Ɠ����Ӗ��ł͂Ȃ��A���̓����A�������_�ɂ͂��Ȃ����p�̏p����{�Ƃ��Ēm���Ă��āA��������q�l�ɋ����邱�Ƃ̏o����m�E�n�E������A����ł͎��ۂɂ�������i�Ƃ��ĕi�������Ă���悤�ȓX�̂��Ƃ������̂ł͂Ȃ����낤���B �������Ȃ��̓X�̂��q�l�����̖{���̖���m��Ȃ��悤�Ȑl�������悤�ł���Ȃ�A���̂悤�Ȃ��q�l�ɑ��Ċȕւň��Ղȃ��[�J�[�̏o�������i�������߂���̂ł͂Ȃ��A�N�x�̗ǂ��{�̋��ł���Ȃ���A�i���̍����{���u���̋���i�������āA���̏��i�̗ǂ������q�l�֒n���ɃR�c�R�c�Ƌ����Ă������Ƃ��d�v�ł���A���̂悤�Ȑ₦�ԂȂ��w�͂Ƃ����̂���X�ɑ傫�Ȕ���ւƂȂ����Ă������Ƃł��낤�B |
�ȏ�̂悤�ɋL���āA�M�҂�FISH FOOD TIMES �̎傽��ǎ҂ł��鋛�̔̔��ɊW����l�B���u���̑S�ĂʂȂ����������Ƃ̏d�v���v���ēx�������ׂ��ł���A���̂��Ƃ����H���i�̗���Ƃ��ď���҂ɂ�������`���Ă����Ăق����Ƃ̂��Ƃ����̎��ɋL���Ă�������ł���B
�p����̌���
���̑S�Ă��������Ƃ����Ӗ��ł͏ے��I�Ȃ��Ƃ�����B����́u�p����h�g�v�ł���B�ȉ��̉摜�̂悤�Ȏp����h�g�Ƃ����̂́A�h�g�Z�p���u�����Ȉ�̐��E�ɂ܂Ƃ܂������I��i�v�ł���A�h�g�̔��������̖ʂ����łȂ��A��������\�����邽�߂ɓ����ȊO�̂قƂ�ǂ̕��ʂ��Z�I�I�ɋ�g���Ă�����I�ȏ��i���ƌ����邾�낤�B
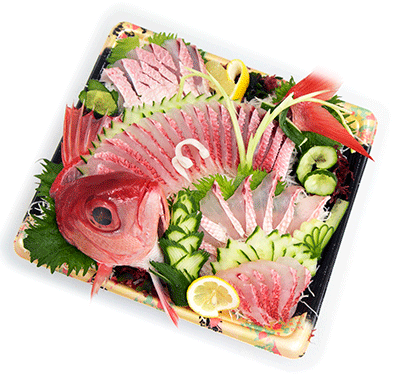
�n�}�_�C�i�A�J�}�`�j�p���蓒���h�g
�������A���̂Ƃ���p����h�g�Ƃ������i���u���_�ȋ������������݁v���ƌ��߂��閳�����ȏ���҂�����悤�Ȃ̂��B���̍l���͎p����ɂ͌������Ȃ������⒆���A���r���Ȃǂ̓��_�ȃS�~�ɂȂ��邾���ŁA����Ȃ��͎̂ז��ȏ���ł����Ȃ��̂�����K�v�Ȃ��Ƃ����l���ł���B
���Ԃ���X�̐����҂Ƃ��Đ��S�~�Ȃǂ��o���邾�����炵�����Ƃ����u��w�I�ȍ����I���z�v���Ǝv���邪�A����͂܂��Ɂu�g���W���Ȃ��v�l���ł���A���{�Ő̂��瑸��Ă�������╗���Ƃ������̂������������̏o���Ȃ��Ȏv�l���ƌ��������Ȃ����낤�B
�p����h�g������ȑ����������o���Ȃ��l�Ƃ����̂́A�����̂��ׂĂɂ����āu���������ǂ����v�Ƃ����ϓ_���l�����鎖�Ȃ��s�����A���������⍇�������ŗD�悵�Đ������Ă���̂��Ǝv����B
�������⍇�����̊��o��D�悷��l���炷��Ǝp����h�g�̔��I�ȋ����Ƃ����̂̓��_�Ȃ��Ƃ�������Ȃ����A���̂����ۂ��ʼn���ł̋��̓��������̂Ă��Ɋ��p����Ƃ����D�܂����H�K�����炷��ƁA����́u�t�̈Ӗ��ō����I�v���Ƃ�������̂ł���B�܂�A�{���͂��Ƃ��Ǝ̂Ă��Ă����������Ȃ����⍜���u�������̎����v�ɖ𗧂��Ȃ���A�̂Ă�ꂸ�ɓY�����Ă���̂�����A�����悤�ł̓v���X�A���t�@�ׂ̖����̂Ƃ��邱�Ƃ��ł���̂��B
���Ƃ���ƁA����̐l�ɂƂ��Ďp����h�g�ɋ��̓��⍜�����i�ɓY�����A���������ɍ����Ȃ���Α傢�Ɋ��}����鏤�i�Ƃ��ĕ��y���Ă��Ă����������Ȃ��͂����B����������̋�����Ŏp����h�g���������鎖��100���ɋ߂��m���Ŋ��҂ł��Ȃ��̂ł���B
���̗��R�͖��m�ł���B����̎h�g�͐̂���卪������g�p���Ȃ���@����{�Ƃ��Ă����̂ŁA�卪������ӂ�Ɏg���ċZ�I���Â炷�p����h�g�Ƃ����̂́A���i���̔��z�̈�Ƃ��đ��݂��Ȃ�����Ȃ̂��B�{�y�ł͓�����O�̎h�g�̃c�}�Ƃ��Ďg���~��̑卪�́A�̂��牷�g�ȉ���̒n�Ŏ�ɓ����̂������̈�������̂ŁA�卪������g��Ȃ��h�g���嗬�ƂȂ��Ă����̂ł���B�����������̉���ł͎p����h�g�����ł͂Ȃ����ʂ̎h�g���i���A���̉摜�̂悤�ɂǂ��̓X�ɍs���Ă��卪������g��Ȃ��h�g�����ʂ�����A�卪������ʂɎg���p����h�g�����鎖���o���Ȃ��Ƃ����킯�ł���B

���������̂��瓖����O�ɂ���h�g�Z�@�Ƃ����̂͂ق�100����������ł���A��������g���[�ɉ����ɕ��ׂ邾���Ȃ̂�����A�ǂ��̓X�̎h�g���o���オ��ɑ傫�ȍ��͂Ȃ��A�h�g�̕t�����l�ő��Б��X�����ʉ����邱�Ƃ͓���Ȃ�A���������X�����h�g�̔��グ�ŏ��Ƃ��Ƃ���Ǝ�������{�����[���≿�i�̋����ɑ��炴��Ȃ����ƂɂȂ�̂ł���B
�M�҂͉���̂���X�[�p�[���Y����̎w�����J�n���č��N��11�N�ڂɂȂ邪�A���̎w���|�C���g�͂����ɉ��i���������Ȃ��čςޕt�����l�̍������i�����t�����A�ǂ̂悤�ɂ��đ��Ђ��ǂ����Ȃ����x����z���グ�邩��O���ɒu���Ďw�����Ă����B


���̈�Ƃ��āA�h�g���i�ɂ��Ă͋Z�p�I�ȍ��ʉ��������o����u�卪������g�����h�g�v�𐅎Y����ŋ������i���Ă����B���̌��ʍ��ł͓��ɑ卪������g��Ȃ���Εt�����l���o���Ȃ��u��^�h�g������v�Ȃǂ̏��i�ɂ��ẮA�M�҂��w�����Ă���X�[�p�[�͉��ꌧ���̂ǂ̗ʔ̓X�Ɣ�r���Ă��A�ǐ��������Ȃ��D�ʂȃ��x���܂ł��Ă���Ǝ������Ă���B
���̂悤�ɔ��f�ł��闝�R�́A��������卪������g�����h�g���i���قƂ�ǔ���ɏo���Ȃ��X���A�~����ɂȂ�������ƌ����ċ}�ɑ卪������g��10�_�����15�_����Ƃ������傫�Ȏh�g����������ɍ�邱�Ƃ͂ł��Ȃ�����ł���B�卪��������p�����h�g�����ɐ�����邱�Ƃ́A�ȒP�����Ɍ����Ă�����قNJȒP�ȋZ�p�ł͂Ȃ��A���ɉ��̐[���@�ׂȋZ�p�̈�Ȃ̂ł���B
��摜�̂悤�ɁA�M�҂��w�����Ă���X�[�p�[�̋�����͑卪������g�����h�g�����Б��X���������ƖL�x�ɕi��������Ă��邪�A�ł͎p����h�g�������������ł��邩�ƌ����A�c�O�Ȃ��炻�����������͂Ȃ��B �����y�[�W�擪�̊����摜�̂悤�Ȏp����h�g���i��������Ă�����A���ꂪ���邾���ő��Б��X�Ƃ̈Ⴂ���X�ɖ��m�ɑł��o���Ė��͓I�ȋ�����ɂȂ�͂����B
�ܖ��ܐF
���̊����摜�̃q���_�C�i�N���L���}�`�j�p����̍����H�����摜�Ő�������ƁA

�P�C����������r���܂ň�̂ƂȂ����������A�e��̍��߉�����E���ւƗ��̓I�ɍ����N�����Đ�����B

�Q�C�����̏�ɑ�t�ƃL���E���̃X���C�X����ׁA�卪����������̑��ɂ��ĂQ�i�ɐ���B

�R�C�P�i�ڂ̑卪����ɏ�g�̕�����������ɐ���A���g�̕�����͂Q�i�ڂ̑卪����ɐ������B
�������Ďp����h�g�����̂����A��͂�p����Ƃ����̂͌����ڂ��d�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ŁA������邾���ł͂Ȃ������Ƃ��Ă̑卪����̑��ɁA��t�A�L���E���A�������A�l�Q�A�C���A�ȂǂŔ��������藧�ĂȂ���Ή��l��\�����邱�Ƃ͏o���Ȃ��B�����ߏ�ȂقNjX�������藧�Ă��̂���̉摜�ɂ���n�}�_�C�i�A�J�}�`�j�p����ł���A��r�I�ȑf�ȗႪ�q���_�C�i�N���L���}�`�j�ł���B
�����ɂ͈ȉ��̉摜�́u�����炢�v��Y���Ă���B
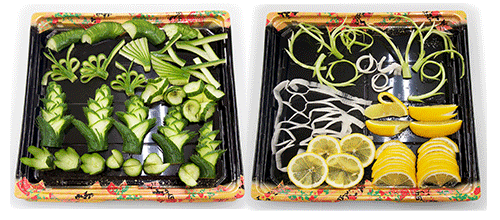
��̉摜�ɂ̓L���E�����ɂ��Ĕ���ɂ����X���C�X�͓����Ă��Ȃ����A����̓L���E�������炢�̒��ł͈�ԃx�[�V�b�N�Ŏg�����肪�ǂ����p����Z�@�ł���A�挎�� FISH FOOD TIMES ����30�N�S���� No.172 �ɂ��̂����炢�̍����H�����摜�ŏЉ�Ă���̂ŎQ�l�ɂ��Ăق����B
���{�����͌ܖ��ܐF����{�ɂȂ�ƌ����Ă��邪�A�ܖ��Ƃ͊Ö��E�_���E�����E�ꖡ�E�|���ł���A�ܐF�Ƃ͔��F�E�ԐF�E���F�E�ΐF�E���F�̂��Ƃł���A�a�H�͂��̌ܖ��ܐF�����ʓI�ɔz�u���邱�ƂŁA��������������������悤�ɂ��̔�������\�����Ă���̂ł���B
�Ⴆ�Έȉ��̉摜�͓V�R����g�����g�����u�V�R��p�������h�g�����킹�v�Ƃ�����i�����A�����炢�͍T���߂ł��l�X�ȋ��̖��i�ܖ��j�ƐF�i�ܐF�j������邱�ƂŁA��摜�̃q���_�C�p��������h��ō��ɂȂ�A���̕����F�X�y���߂����ň�i�Ɣ������������Ɗ�����̂ł͂Ȃ����낤���B
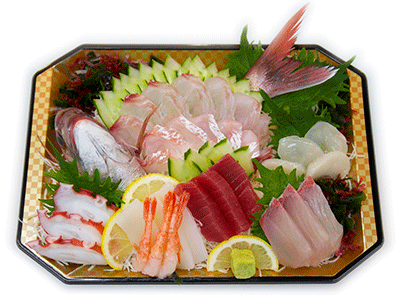
�h�g�����̕ϓN���Ȃ������I�ȗe��ɒ[�ɐ��ĕ��ׂ������̍����I�Ō����I�ȏ��i�ƁA���̉摜�̂悤�ܖ��ܐF��O��ɂ����Z�@���Â炵�āA������Ԃ��������Ă��鏤�i�Ƃ͖��炩�ɑ傫�ȈႢ�����݂��Ă���̂͒N���������ł���ł��낤�B
������Ŏh�g���i�̔��グ��L���̂ɁA�����I�Ō����I�Ȏ�@�ł͋Z�@�̌��E���璼���ɔ��グ�̕ǂɂԂ��邱�ƂɂȂ�A�{�����[�����o���������������Ƃ������@�ɗ��炴��Ȃ��Ȃ�B��������摜�̂悤�ȏ��i������͂�����A���̐�ɂ�����X�ɐi�������Z�@��m�b���o���č��o�����Ƃ��s�\�ł͂Ȃ��̂ł���A�܂��܂������̉\��������ł���Ƃ�������̂ł���B
���q�l�́u�O�����ۂ��v���̂��Ƃ����O��ɗ��Ȃ�� �A���q�l��O�������Ȃ��悤�Ȏ��ł������邱�Ƃ����グ��L�������邱�ƂɂȂ���͂��ł���A���̂��߂ɂ͂��q�l�̃j�[�Y�ɉ����ď��i��ω��������邾���́u�m�E�n�E�ƋZ�p�v�������Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�u�����Ƃ͕ω��K���Ƃł���v�Ɗ��j������l����������ǂ��A�ω����O���₷�����q�l�̚n�D�ɑΉ��ł���悤�A���������肷��l�B����������͂����Ă����Ăق������̂��B
���Y�R���T���^���g����m�N�����Ɉ�x�X�V���Ă������̃z�[���y�[�W�ւ�
���ӌ��₲�A���́@info@fish food times
�X�V�����@����30�N 5�� 1��