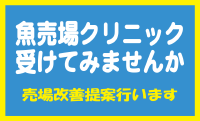�悤���� FISH FOOD TIMES ��
�N���R���T���^���g�������X�V���鋛�̒m���ƋZ�p�̃z�[���y�[�W

����29�N 1�����@��157

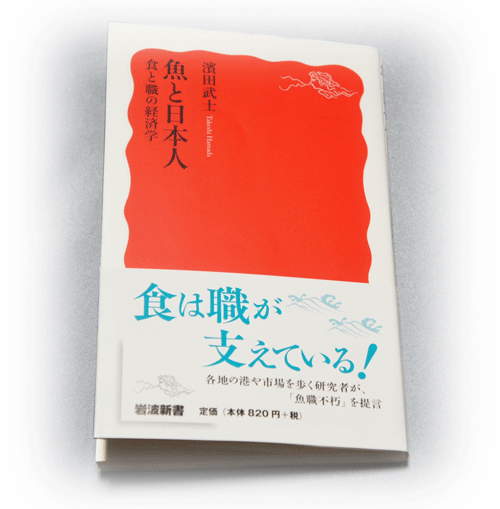
���E�s��
���ɊW����l�͕K�ǂ̖���
���ɊW����E��œ����ǎ҂̊F�����E�C�Â��閼���u���Ɠ��{�l�v�i�H�ƐE�̌o�ϊw�j��g�V���� �k�C�w����w�o�ϊw������ �_�c���m������N10���Ɋ��s���ꂽ�B
�M�҂͔�������ĊԂ��Ȃ�11���ɂ��̖{��ǂ�ŁA����͋��ɊW���ē����Ă���l�X�ɂ͐���ǂ�ŗ~�����{���Ɗ����A���̂���FISH FOOD TIMES�ł��̗v����Љ�邱�Ƃɂ����B
����̖ړI�́u������L�b�J�P�ɂ��̖{�ɋ����������A���������������ۂɖ{���w�����i820�~�j�A��������Ɛ��ǂ��āA����d���̗ƂƂ��Ă��炢�����v�Ƃ������Ƃł���B
���ꂩ�炱�̖{�̗v����Љ�Ă����������A��{�I�ɒ��҂̕��ӂȂ�Ȃ����߂ɁA�M�҂�����ɕ��͂̏���������悤�Ȃ��Ƃ͂��Ȃ�����ł���B���̗��R�͕����̑O��̊W�����ĕM�҂����͂����邱�ƂɂȂ�̂�����A���҂��`���������ӂƂ͈Ⴄ���߂�M�҂����邱�ƂɂȂ邩������Ȃ��Ƃ������ꂪ����A�ǎ҂̕��X�͕K�����̖{���w�����āAFISH FOOD TIMES�ł̉�����L�ۂ݂ɂ���̂ł͂Ȃ��A�����Ȃ�̉��߂����Ăق����̂ł���B
����ł͂��ꂩ��A�{�̗v��Ɖ���ɓ����Ă������B�܂����͂̋��H�Ƌ��E�̍��ňȉ��̂悤�ɋL����Ă���B
���H�́u�H�ׂ�v�Ƃ����s�ׂł���B������ʂɁu���H�v�ɂ͋����u�T���v�u�����v�u��������v�ȂǂƂ����s�ׂ��t�����Ă���B����Ɋۋ��Ȃǂ��ꍇ�́A�����◿���̂���������낢�날��̂Łu�����Ă��炤�v�Ƃ����s�ׂ��t�����Ă���Ƃ�����B�Ƃ��낪�X�[�p�[�}�[�P�b�g�̑N���R�[�i�[�ɂ����ẮA���̂悤�Ȃ��Ƃ肪�����Ȃ��Ȃ��Ă���B �̂͑N���X���X�[�p�[�}�[�P�b�g�̈�p�ɂ���A�����߂����b�͂��������A�����ł͂��̂悤�ȃX�[�p�[�}�[�P�b�g�͏��Ȃ��B�N���R�[�i�[�ɂ͔����t���̊ۋ����܂�ȑ��݂ɂȂ��Ă���B�N���ł��g���[�p�b�N�ɓ����ꂽ�ؐg���ނ������B�������Ȃ��Ɣ���Ȃ��炵���B�����̏��ނ́A�h�g�p�A�t���C�p�ȂǁA�ǂ����ĐH�ׂ���悢�̂������Ƃ킩��悤�ɕ\�����Ă���B�֗��ł���B�����Ȃ��Ă悢���A�������Ĕ��f���Ȃ��Ă悢�B |
|---|
�������_�c�����́A���{�̋��H��������E�\���u���E�v�Ɩ��t���Ă���B
�n��o�ς̊j�ƂȂ藠���Ƃ��ēs�s�̔ɉh���x���Ă������Y���̎Y�n�s��Ə���n�s��͂��̋��E�������ɏW�����Ă���Ƃ��Ă��邪�A�����ȉ��̂悤�ɋL���Ă���B
�Y�n�s��͎Y�n�̒n��o�ς̊j�ƂȂ�A����n�s��͒n��o�ς����łȂ������Ƃ��ēs�s�̔ɉh���x���Ă����B�����s�ꂪ�Ȃ���ΎY�n�̔��W��s�s�̌`����g��͂��蓾�Ȃ������ƌ����Ă悢�B |
|---|
�ǂ����Ă��̂悤�ɏk�����Ă������̂��A���̎���w�i�Ƃ��āA
���{�̏A�Ɛl���́A��㒼��͑�1���Y�ƕ��傪�������߂Ă����B�������x�o�ϐ�����ʂ��āA�ꎟ�Y�Ƃ���Y�ƂցA�����ĎO���Y�ƂւƃV�t�g�����B�����āA���̉ߒ��̂Ȃ��œs�s�ɕx���W�����A���̂����o�ς̎��R�����ۉ��������i�߂�ꂽ���ƂŐH�������n�������Ɍ��炸���E�ɋ��߂�悤�ɂȂ����B |
|---|
�������ē��{�̐����҂́A����H�ׂ悤�Ƃ���ƌv�ւ̎x�o�i���H�j�͌��葱���Ă���A�Ƃ��Ă���B
���H�Ƌ��E�̍Đ��ւ̓����l���邽�߂ɂ́A
�u�H�v���u�E�v���I���͎��R�ł���B�u���H�v��u���E�v����������ɂ́A�l�X�������D��ŐH�ׂ�����肾���A������舵���d�������͂���d���ɂȂ�悤�ɂ��邱�Ƃ��ۑ�ƂȂ�B �������A����ꂽ���������Q���Ă��d�����Ȃ��B���H�Ƌ��E�̕����̂��߂ɂ͉����K�v�Ȃ̂����Âɍl���Ă����˂Ȃ�܂��B���̂��߂ɋ��H�Ƌ��E�̖��͂ƌ�����m��A�O���[�o���o�ς̂Ȃ��ɖ��v����H�ƐE�̓N�w���܂��[�߂Ă����K�v������B |
|---|
���͂ł͈ȏ�̂悤�ɋL����Ă���B
�H�ׂ�l����
���݂Ɏ���H�̕ω�������ƁA��ォ��u���ّ��v�ƌĂꂽ�T�����[�}�����т��������Ċj�Ƒ��������������A���オ�i�ނƒ��H�̍��������i��ŃR���r�j�Ńp���₨�ɂ�����čς܂���悤�ɂȂ�A�X�ɐH�̍��������i��Ŕ������ʂ������āA�Ƒ��c���̒��H��[�H�ł���u�ǐH�v�i��l�ŐH�ׂ�j��u�H�v�i���ѓ��ł��ʂ̐H�ו����ʂɐH�ׂ�j�������Ȃ��Ă����B���̌��ʁu�H�v�͗�������l�ƐH�ׂ�l���Ȃ��s�ׂł���͂��Ȃ̂ɁA���̎Љ�I�ȍL���肪�u�H�v������������Ă���A�ƒ��҂͏q�ׂĂ���B
�H�������ϖe���钆�ōł������Ȍ��ۂ́u�H�̊O�����v�ƌ����A����͒P�g���т����ł͂Ȃ����ʂ̐��тł��ƒ�O�ŗ������ꂽ���̂�H����X�������߁A�t�@�~���[���X�g�������]���i�Ȃǂ͉Ƒ��̂��߂̏ꂾ���ł͂Ȃ��A�Ǝ��J���̕��S���y����������悤�Ƃ�����̂ł���A�u�H�̊O�����v�̃r�W�l�X�^�[�Q�b�g�͋��������т�P�g���т����ł͂Ȃ��A����Ґ��тɂ��L�����Ă���A�ƋL����Ă���B
����Ȓ��ŋ��̏���ʂ͋}���ɗ�������ł���B
����Љ�ł́A���d�˂�Ɠ���������n�D����u������ʁv������ƌ����Ă������A���₻�̗��_�͋^��Ƃ���Ă��Ă���A�H���ƐH�̊O�������}���ɐi�݁A�ƒ���ɃX�g�b�N�����H�ނƂ��Đ��N�H�i���������A�Ⓚ�H�i����H���i�̊����������Ȃ�������̒��ŁA�����̂����ۋ��̏���ʂ͐L�т�͂����Ȃ��A�Ƃ��Ĉȉ��̂悤�ɂ����͂���Ă���B
�s�s�����҂ɂƂ��ċ��͖ʓ|�ȑ��݂ł��邩������Ȃ��B |
|---|
���̂悤�ɋ��H�͐l�����������₷���v�f�𑽂������Ă���̂����A����ł����H�����悤�Ƃ���l�Ƃ��ẮA�Ⴆ�Ό��N�ȐH�ނƂ��ċ���I�Ԑl�A�܂��͋��̔���������m���Ă��č����ȋ����D��Ŕ����l������Ƃ��āA
�U��Ԃ�ƁA�H�i�s��ɂ́A��y�ŁA�֗��ŁA�����āA�ŐV�̐H�i���w�ŊJ�����ꂽ�����ς݂̃��g���g��Ⓚ�H�i���邢�̓t�@�X�g�t�[�h�����Ă���B�J��Ԃ��ɂȂ邪�A��͂莞�Ԃ��ԁA�����̏K���Ɏ��Ԃ�v���鋛�H���p��Ă����̂��������Ȃ��B �����A���̂��������̊�т��ǂ̂悤�Ȃ��̂���m���Ă����Ƃ�����A��тɂ��ǂ蒅�����߂ɁA���Ԃ������āA�r���āu�N���̕ǁv�����z���悤�Ƃ��邩�A���ꂪ�ł��Ȃ���A�����l�ɑΉ����Ăł��H�ׂ�A�Ƃ������ƂɂȂ�B |
|---|
�����҂ɔ���l����
�����������œ��{�ł́u���H���y�����v�����������Ă��āA�s���A���ƒc�́A�����s��A���Y�֘A�c�̂��������̃C�x���g���e�n�ŊJ�Â��Ă���B����͐[���ȁu������v��h�����߂̊����ł��邪�A���ǐ��Y���s��S�̂͐�ׂ肵�Ă��鎖���ɕς��͂Ȃ��u����H�ׂ�l�v�����炳�Ȃ��悤�ɂ���̂��u���E�v�̉ۑ�ƂȂ��Ă���B
���̑����͓V�R�����ł���A������H�ނƂ��ċ���ł���͉̂ߍ��Ȏ��R���̒��ŐH�ނ��̎悷��l�����āA����𗬒ʂ����Ă���u���E�v�����݂��邱�Ƃ��m���ė~�����ƋL����Ă���B
�܂����́A�G�߂�n��ɂ���Ď��̂̂�����قȂ�B���̂��߁A�������ł��A�G�߂�ꏊ�ɂ���ĐH�ו����قȂ�B�{�̋��͂�������������A�G�߂͂���̋��ł��H�ו��������Ŕ��������Ȃ�B�܂��������łȂ��Ă��A�����I�ȋ������������H�ׂ郌�V�s�͂��낢��ƍl�����Ă���B |
|---|
���̎������Ԃ�ǂ��Ă����ƁA�����̑����͎��R�̂��ƂȂ̂Ől�Ԃ��R���g���[���ł�����̂ł͂Ȃ��A���g������鋛����H���l��������A�����p���̊J������m�̋��̐V���ȗ��p���@�̊J���͐̂������s���Ă��邪�A��͂�����H�ׂ�l�𑝂₷�ɂ́u����l�v�ɂ����҂������A�Ƃ��Ă���B
����������s�X�n�ɂ͑N���X�̎p�͂قƂ�nj���ꂸ�A���H�g��͑�^�X�̑N���e�i���g��X�[�p�[�̑N������ɑ��������Ȃ��悤�ɂȂ��Ă��Ă��āA�H��[�����c���2008�N�x�̒����ɂ��ƁA�q�������e��77�����X�[�p�[�ŋ���ނ��Ƃ����������ʂ��o�Ă���炵���B
�Ƃ��낪�A�X�[�p�[�̑N�������1990�N��ȍ~�ɉ~�����e�R�ɂ��ėA�����Y���̎�舵�����������A����炪�N������̎���̂悤�ɂȂ��Ă���������ȉ��̂悤�ɋL���Ă���B
80�N��܂ł̗A�����Y���̎d����́A���Y�̕s������⊮���邽�߂ƌ����Ă����B������90�N��Ȍ�̂���́A�����ƊE�̔��W������A��ʃ��b�g�i��ʐ��Y�E��ʗ��ʁj�������\�ɂȂ�����A�~����Ƃ����ב֊�����`���āA�d���ꌴ�����}����ꂽ�r�W�l�X���f���ƂȂ����B���i�i���͂�������A�����Y���́A�X�[�p�[�}�[�P�b�g�̒I���獑�Y���Y���������̂��鑶�݂ƂȂ����̂ł������B�����������̗A�����Y���́A�X�[�p�[�}�[�P�b�g�̑N������̒�ԕi�ƂȂ����B�������N������ɂ����Ă�����͖{���̑N���ł͂Ȃ��B2000�N��Ȍ�A�n���C���ݍ���I�[�X�g�����A�Ȃǂ����A����Ă���{�B�N���}�O����{�B�~�i�~�}�O���̐��N�i�����������A�����������A�قƂ�ǂ��Ⓚ���Y���ł��邩�A�𓀕i�ł���B���{�ʼn��H���ꂽ���i������A���n�ʼn��H���ꂽ���i������B�E�E�E���������E�E�E�������������ƈ��肵�������͂̂���A�����Y���ɑ��āA���i����������V�R���Y���͎�舵���ɂ����B��Ԃ̃}�A�W�A�T���}�Ȃǂ̐��ނ�A�}�O���ށA�����ă}�_�C��u���Ȃǂ̗{�B���͋G�߂̍ʂ���o�����߂ɔ̔�����Ă��邪�A���̑��̓V�R���ɂ��ẮA�ƂĂ������Â炢�̂łǂ����Ă����Ȃ߂ƂȂ�B |
|---|
�����ăX�[�p�[�͋������������钆�ŁA�R�X�g�팸�Ŏ��v�͂����悤�Ƃ��āA�l�����}�����A��ԕi���ʂɔ̔����Ď��v�����߂悤�Ƃ����X�������܂�A�d���ꉿ�i�̗}�����ʎd����ɂ���Ď������悤�Ƃ��Ă������A���̃r�W�l�X���f���͐��Y���̔��̑��i�ɂȂ��Ă͂����Ȃ������B��ʔ̔��Ɍ��������X���o��悤�ȁA���܂蔄��Ȃ����Y����I�ɕ��ׂ�킯�ɂ����Ȃ��̂ŁA�I�ɂ͓���݂̂����Ԃ̐��Y�������u���Ȃ��X�������܂�A���ʂƂ��Ĕ������q�͋����u�H�ށv�Ƃ��ĒT���y���݂��Ȃ������ƂɂȂ��Ă��邱�Ƃ��A���̂悤�ɏq�ׂĂ���B
��Ƃ͈Ⴂ�A���͗����̕K���i�ł͂Ȃ��A�n�D�i�I���i�������B�܂������͌����ɂ��킹�Ĕ����Ώۂł���A���������ɂ����Đ����҂͎��O�ɔ������̂����߂�B���͔���ɍs���Ă���A�������ǂ��������߂��Ă���P�[�X�������B |
|---|
�܂��A90�N��ȍ~�ɋ}���Ɏ��v���ނ��Y�������Ƃ��āA�C�s��ςO��V�F�t�Ȃǂ��c�ޗ������A���i���A�z�e���̍������X�g���������グ�Ă��āA���Ă����̓X�͐ڑ҂Ő��藧���Ă��鑤�ʂ����������A90�N��ȍ~�Ɋ����ڑ҂⊯���ڑ҂����ƂȂ��Ďx�o�k���̑ΏۂƂȂ��Ă���͐������Ȃ����A�O��V�F�t�̊���̏�Ƃ��Ă̊��͂��Ȃ��Ȃ�A���{�̐��Y���̋����`���͂̈�p������āA���Y�������s��⋙�ƌo�c�̊��͂�������邱�ƂɂȂ����A�Ƃ��Ă���B
���̈���ŁA�����͒n�Y�n���u�[���������Ȃ�A�_���Y�������������i���Ă��āA2013�N�ɂ͑S����247�̋����������������L���A�N��1,358���l�������𗘗p���Ă���A���̐����͌��݂��~�܂��Ă��Ȃ��悤�ł���B
�܂��A�����X�[�p�[�̋����ꂪ��킷�钆�Ńf�p�n���̑N�����X��[�J���X�[�p�[�͑S���e�n�őP������Ă���A���ɐV������{���Ƃ���p�㋛�ނ̔̔����@�́A�N���A�ۋ������ł͂Ȃ��A���H�i���܂߂ċ���H�ׂ����Ƃ����q�w�ɂ�������Ή����Ă��邱�ƂŒ��҂͒��ڂ����Ă��邵�A���[�J���X�[�p�[�̑�\�Ƃ��Ă͈��m���L���s�̃T�����l�ɂ����ڂ��Ă���B
�S���e�n�ɂ͒n��ɖ��������グ��L���Ă��郍�[�J���X�[�p�[������A���Y���̔̔����Ζʔ̔��ɗ͂�����Ȃǂ��Ĕ��グ���L�тĂ����Ƃ����邪�A�K���������[�J���X�[�p�[�̋����ꂪ�傫���ׂ����Ă���Ƃ����킯�ł͂Ȃ����R���ȉ��̂悤�ɋL���Ă���B
���̂����͌���Ή��ł���u�ǂ�Ԃ芨��v�ł�����B�}�j���A�����ł���悤�Ȃ��̂ł͂Ȃ��B�ׂ���������Ƃ͌�����Ȃ��B����ł��A�N�x���A�����̂悳�A�C���̂悳�A��̌��������Ă��邩��A���܂߂ɔ�����������q�Ƃ��܂��܂ȋ����W�܂�B�l�������Ⴍ�Ă��A������]�������A����邱�Ƃ��ł���Η��v�͏o������B |
|---|
�S���̒��������s����n�������s����A���Y���̎�芪�����͌��������ރ��[�h�������Ă���B���Y�������ł͂Ȃ��ʕ������l�̌X���������Y���͐ʕ��ȏ�̊�@�ɒ��ʂ��Ă���B���[�̏�����O�H�̔̔��͂̒���������s��̉��i�`���͂̎コ�ɒ������Ă���̂ŁA�Y�n�̏o�Ǝ҂͉����s��ւ̏o�ד��@����܂邱�ƂɂȂ�A���ʂƂ��ĉ����s��ւ̏��i�o�R����������邱�ƂɂȂ��Ă���B
�����̒��������s��ƒn�������s��̎��Ԃ��L����Ă���u��R�� ����n�ʼn����l�����v�ɂ��ẮAFISH FOOD TIMES �ł̃T�C�g�Ώێ҂ƖړI���炷��ƁA���̕����̉���ɂ��Ă͏ȗ��������Ǝv���B���������̑�S�͂́u�Y�n�ł����l�����v�ɂ��Ă͊ȒP�ɐG��Ă������B
�S����825���݂��Ă���Y�n�s��́A��ɐ��Y�҂��o�ׂ���s��ł���A�����ł��戵�ʁA���z���N�X�����Ă��āA�S���ɂ���قǑ����̎Y�n�s�ꂪ���U���Ă���͖̂��ʂ��Ƃ̍l������A����܂œ��p�����s���Ă������A���̐�����̌v��͂���悤�ł���B
����������ŁA�Y�n�s��͒n��ɂƂ��Ă͊ȒP�ɂȂ������Ƃ̂ł��Ȃ����݂ł�����A���Ƃ⋛�̏��H�ƂȂǂƈ�̉������n��̎Y�Ƌ��_�ł���A�n��o�ς��x���鑶�݂ł�����B���̎Y�n�s��Ƃ����̂́A
�C�������āA���Ƃ��������������āA�����ɋ��������āA�������l�������ɂ��āA���܂��o�ρA�������������̂��Y�n�s��B�����ɂ����ĕ����I�ɂ��o�ϓI�ɂ��A�V���{���b�N�ȑ��݁B����͎��R�Ƌ��E�Ƃ������Ƃ��d�Ȃ肠���A���j����Č`�����ꂽ�u�s��v�ł���A���������Ǝx�z�����邽�߂́u�s��v�ł�����B���ꂪ���܁u��剻�����O���[�o���s��v�Ɉ��ݍ��܂�A�b���ł���B |
|---|
�Y�n�ʼn��H����鐅�Y���H�i�͋����̕�炵�Ɩ��ڂȊW������A���Y���H�Ǝ҂ɂƂ��Ă��̐��i�J���͎d���̑�햡�ł�����A����l�̖��o�Ƀ}�b�`������悤�ȐH�i���J�����ꋟ������Ă������A�`���I�Ȑ��Y���H�i�̎��v�͏k���������A���Y���H�Ƃ����葱���Ă���B
���Y�ƊE�̘b�ɂȂ�Ƌ��ƎҐ��̌��ۂ��肪���ڂ���邯��ǂ��A�t�����l�Y���Ă������H��������l�̏ł���A���i�������Z����ɐV�������i���J�����Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ŁA�����ł���̐l�C���i�����ł͈��ׂł��Ȃ��̂ł���B
�ߔN�͐H�̈��S�E���S�������悤�ɂȂ�A�ٕ�������h�����߂̋����T�m�@��ٕ��������u�Ȃǂ̍����@�B���u�����Ȃ���Ȃ�Ȃ����A������̊m�ۂ��N�X����ɂȂ��Ă��Ď�芪�����͂ǂ�ǂ����Ă���悤���B
����l����
���̂悤�ɎY�n�s��ł̊��������i�s���Ă��邪�A���̎s��ɋ��𐅗g�����鋙�t����芪�������ǂ��Ȃ��Ă��邩�ɂ��Ă��A��T�́u����l�����v�̒��ŋL����Ă���B
���҂��k�C���̒ꌚ�Ԃ̋��ŋ��D�ɏ�D�����������̑̌��A�����Đΐ쌧�̊|�����@�̏��^������ԋ��D�ɏ�����o���Ȃǂ܂��āA���m��ߊC�ł̃J�c�I��{�ނ苙�ɐG��A���D�̋������x�ł���u�咇�E�����E�㕪�������v��A���ƌo�c�̎d�g�݂ɂ��Ă�������Ă���B
�D����D���́A�������̋����ǂꂾ�������Ȃ��Ă��A�������Ⴍ������z���Ⴏ��A�o���ӗ~�͌��ނ��A���͐h�������̎d���ɂȂ�B����ł��A���ܑ務������ƑD���͉�R���C���o�Ă���B���ꂪ�ނ�̂�肪���A�C��ł̉Ս��ȘJ�������铮�@�ł���B �����܂ł��Ȃ����A��Ќo�c�ł͎��x�o�����X������A���Z�@�ււ̕ԍς���A�D����R�������҂Ɏx�������ł����A�p�Ƃ�����Ȃ��Ȃ�B����䂦1970�N�ォ�炻���������ƌo�c�҂͌��₽�Ȃ������B70�N��̓�x�̃I�C���V���b�N�����ƌo�c���P�����̂ł���B �o�u���o�ς̕����A�f�t���s���̂Ȃ��ŁA�Ƃ���90�N��㔼����̗A���ʂ̑��傪�A�傫�����Y�̋��������������B����ɁA���̍����Z��@��w�i�ɋ��Z�@�ււ̍s���ē���������A�݂��a��Ƒ݂��͂��������s����B������2005�N�Ȍ�̔R�������B���̊Ԃ̌��D�i���D���p��•�T�ނ��邱�Ɓj�͒����������B |
|---|
��������D�����Ƃ͏��ł��A�k�m�T�P�}�X�����Ԃ̗��j��2015�N�ɕ����A���V�i�C�̈Ȑ�������ԋ��ƁA�k�m�̖k�m�]��������ԋ��ƁA�씼���ł̉��m�C�J�ނ苙�ƂȂǂ́A�ȑO�̐��S�NjK�͂��琔�ǃ��x���ɂ܂ŗ�������ł��邵�A���m�E�ߊC�}�O���͂��ꋙ�D�A���m�J�c�I��{�ނ苙�D�A�ߊC�J�c�I��{�ނ苙�D�̐����������Ă���A�������������E���m���D�̌��D����1977�N�ȍ~��30�N�Ԃ�6,000�Ljȏ�A���ɖ�80���ȏ㌸���Ă����Ƃ̂��ƂȂ̂��B
����ŗ{�B�Ƃɂ��Ă��G��A�{�B�Ƃ͈���I�Ōv�搶�Y���\�ƌ����Ă��邪�A���Ԃ͕ϓ�����C�ہA�C�̊��̒��ŁA���Ǝ҂��ǂ���Ƃ��邩�A��Ԃ̂������A�r�̍��Ő��ʂ͕ς�邱�Ƃ�m���ė~�����Ƃ��Ă���B
�C�ʂ��g�����{�B�Ƃ��A�V�R�������l�鋙�Ƃ��u���L���ʁv�ł���C�ɐ������鋛��ނ́u���啨�v�ł���A�����ɏ��L���͂Ȃ������Ƃ��Ď��R�ɍ̎悷�邱�Ƃ��ł��邪�A��������R�ɕ��u���Ă����ƗD�Nj���ł̕������������鋰�ꂪ����A�����h�����߂ɋ��Ɩ@������B
���Ƃ��Ǘ����鐧�x�Ƃ��āA���ƌ����ƁA�����ƁA�͏o���ƁA����ȊO�̋��Ƃɕ��ނ���A�Ǘ������͔̂_�ѐ��Y��b�A�s���{���m���A�n��ʋ��Ƌ����g���ɋ敪����A���Y�Ƌ����g���@�A���Y�����ی�@�A���D�@�̊�{�I�g�g�݂�����Ȃ���A���̒����`�������ƎҏW�c�Ɉς˂�Ƃ����A�s�����ɂ��Ǘ��E�ēƋ��ƎҏW�c�̎����ɂ�鑊�݊Ď���g�ݍ��킹�āA���ꗘ�p�̍�����������K���ĕ����ɂ��Ȃ��Ă������������A�Ƃ̂��Ƃ��B
����ɔ����ċ��Ǝ҂�������������I�ɋ��Ƃ��Đ��Y�ł���悤�A�����ƌo�c�ɑΉ��������ƍs�ׂ̋�̓I���@�͗l�X����̂����A�����ł���ɂ��Ă̐����͏Ȃ��Ă��������Ǝv���B
���҂́u���Ƃ�����l�͑�����̂��v�Ƃ������ŁA1961�N����70���l���݂��Ă������ƏA�J�҂�2014�N�ɂ�17���l�ւƌ������A���̏A�Ǝґ�Ƃ��đ傫�ȋ��D�����ł͂Ȃ��A���Y���H��ł��O���l�Z�\���K���Ől��s�������Ă��鎖���𑨂���X��s�������Ă���B
����Ȓ��ŁA�V���ɋ��Ƃ��n�߂����l�����Ȃ��킯�ł͂Ȃ��Ƃ��āA�ȉ��̂悤�ɐh���̕��͂����Ă���B
�V�K�ɋ��Ƃ��͂��߂����l�����Ȃ��킯�ł͂Ȃ��B���͐V�K�ɋ��Ƃ��͂��߂Ă��A���z���Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��ǂ������A�蒅�����Ⴂ�Ƃ������Ƃ��B�s�s�����ɔ��A�C�œ������ƁA���t�ɓ����l�͂���B���������ƂɏA�Ƃ��Ă݂�ƁA���Ƃ̎d���̌������ɒ��ʂ��āA�ς�����Ȃ��ł�߂Ă����l�������B���ꗘ�p�̃��[���A�T���A���D�Z�p�A�����A���[�v���[�N�ȂǁA���낢��Ȃ��Ƃ�g�ɂ��Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B�V���g�Q�̏������ł́A�������̎d���ɂȂ�B�d���͉��������₭���Ȃ��Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B�����������낢���ƂɁA�d���̂����͏\�l�\�F�ł���A�ǂ���琳���͂Ȃ��悤���B���Ƃ͎��R����̌b�݂����R�̂Ȃ��ō̎悷�鐶�Ƃł��邪�A����Ŕg�Q�A���Q�A��������������A�����̗��V���Ȃ�������Ǝv���ʂ�ɂ͂������A��Ɏ��R�ƑΛ����A�v��ʂ�v���ʂ�Ɏ��s�ł�����̂ł͂Ȃ��B�C�̏A���̉�V�����Ȃ���d�������邵���Ȃ��B�莞�œ����d���Ƃ́A�܂��������Y�����قȂ�B |
|---|
�����āA���Ǝ҂́u���J�v�Ƃ����E�\�ɂ��āA�ȉ��̂悤�ɋL���Ă���B
| �i���Ƃ��j�ׂ��邩�ǂ�������̎w�W���낤�B�������A�A�ƑI���̂��߂̎w�W�͑��l�����Ă���B�A�ƂɗD��͂Ȃ��A���̖��͂����ΓI�Ȃ��̂ł���B�ׂ����Ă���d���ł��u���b�N�Ȏd�����ɂ͑����̐l���ς����Ȃ��B�ׂ����Ă��Ȃ��Ă��A�݂�����̐��ƂƂ��Ă��̎d�����҂�����Ȃ�����I�Ԑl�����Ă���B ���́A�����������炵�������Ă������߂ɉ����d���ɂ��邩�ł���A�d���̉��������b����тɓ]���ł��邩�ł���A���̐E�\��g�ɂ��邽�߁A�ɂ߂邽�߂ɁA���X�̐h��������邱�Ƃ��ł��邩�ǂ����Ȃ̂ł���B �����{��k�Ќ�A�D�������Ĝf�r���Ă��鋙�t�������Ă����B�C�ɏo�ċ������Ă��Ȃ��ƁA�h���A�X�g���X�����܂�B��������Ƃ����E�\�́A���t���̂��̂Ȃ̂ł���B���t�͑D�ɏ���ċ��d���̘r���A������������l��A���邢�͗{�B���A���̐��Y�����s��̃Z���Ȃǂŕ]�������Ƃ��Ƀ{���e�[�W���ō��ɒB����B���ꂪ���邩��A�������Ђǂ��Ă��C�ɏo�邱�Ƃ�����B���ꂪ���邩����n���܂ŗ{�B��Ƃ�����邱�Ƃ��ł���B�����ɂ͎������ɂ͖��키���Ƃ̂ł��Ȃ��A���b�オ����悤���B ���������E�\�͑��h����Ă����B�E�\��g�ɂ���Ή҂��������B�������f�t���s���̂Ȃ��ŁA�E�\�͔����@�����悤�ɂȂ����B��s���s���̂Ȃ��ŁA�������ێ����邽�߂ɁA�����҂́u���H�v�͉������A���̑���`���͖͂��炩�Ɏ�܂����̂��B�������ĐE�\���y������鎞��ɂȂ��Ă���A�������ŋ������Ă���l�ւ̌h�ӂ̋C�������Љ�I�ɔ��炢�ł���B �H���͎��������̐g�̂̈ꕔ�ɂȂ�ɂ�������炸�ł���B�s��o�ς̈��Y�ɂق��Ȃ�Ȃ��B �{���u���J�����v�������āu���H�����v�����܂�Ă����͂��Ȃ̂����A����ł͑��l�ȐH�ނ��n�o���ꂽ���Ƃ���A�u���H�v�͏k�����A�u���J�v������ɋ��n�ɒǂ�����ł���B�������A�}�[�P�b�g����āu���H�v�Ɓu���J�v�͐藣����Ă���B �u���J�v�Ƃ����E�\�́u���H�v�������ď��߂ċ@�\����B |
|---|
���҂́u�s��o�ρv���[�܂��Ă����s���قǁu�E�\�v�̈��������u�l�Ƃ��āv�ł͂Ȃ��u���̂悤�Ɂv�Ȃ�A�o�ς̊��͂𗎂Ƃ��Ă��܂��̂ł͂Ȃ����Ƃ������ӎ������������A�g�D���J���̌���ɐ��ʎ�`���L���������ƂŁA�E�\�̖v������i�߁A�����ӗ~��D���Ă���̂ł͂Ȃ����A�����ĘJ���Ɉӗ~���Ȃ��Ȃ�ƁA�o�ς̊��͎͂��߂��Ȃ��̂ł͂Ȃ����A�Ƃ��Ă���B
���͎s��o�ς��ǂ����p���邩���Ƃ��āA
�s��o�ς́A�V�����삪��������̎s���D���Đ�������B����䂦�ɐV�����삪�g��Đ��Y�������ŁA��������͏k���Đ��Y�̃u���Z�X�ɓ���B�����Ċ�������ł͗��v�����������ނ��߁A�u���ʁv�������߂̂�����藧�Ă��g����悤�ɂȂ�B�����Ȃ�Ɗ����̋ƊE���ł͎���W�ԂŃR�X�g�ߌ���l�����̌��A���邢�͌������Ɩ����P�̌����n�܂�A���ʂƂ��đ�Ȃ菬�Ȃ�ƊE�����a瀂������Ă��܂��B���̂悤�ȘA�����e�Ղɑz�肳���B��ÂɊώ@����ƁA�s��o�ς̔��W���̊�������ɂ͂��̂悤�Ȍ��ۂ������Ă���B |
|---|
�ւ��������ꂽ���Y�ƊE���A���H�Ƌ��E�̕����ɂ͂ǂ�����Ηǂ����Ƃ��āA���҂́u�N���̏���E�̔��̍Đ��v�������Ă���B
�����͖{���̊̐S�v�ƂȂ镔���ł���A����FISH FOOD TIMES�ł��̖{���Љ�����Ǝv�����j�ƂȂ���e�Ȃ̂ŁA������������ǂ����҂��L�q����Ă��邱�Ƃ��A�ȉ��ɂ��̂܂Љ�����B
���{�قǑN�����ʂ����W�������͂Ȃ��B������O���邢�͐����҂����N�x�����ߑ��������ʁA�N�x�𗎂Ƃ��Ȃ��N�����ʂ̃��B�����\�z����Ă������炾�B�O���ɂ͂܂˂ł��Ȃ��B �l���l�𗊂�ɂ���A�l���l���ɂ���A�l���l�Ɍh�ӂ��A�����Ď��R����̌b�݂����܂��A���p����B���H�ɂ͂��������A������Ȃ̂ł���B |
|---|
�ȏオ�u���Ɠ��{�l�v�ɋL����Ă�����e�̔����ł���B
���ɐ����͂̂�����e���L�q����A�����ċ�̓I�ɒ�Ă���Ă���Ɗ�����B���Ɂu�Ζʔ̔��̏d�v���v�ɒ��ڂ��Ă���_�͑傢�ɔ[������Ƃ���ł���B
�������͂����Ƃ͈���āA�摜���Ȃ����͂���Ȃ̂œǎ҂̕��X���Ō�܂œǂ�ł��ꂽ���ǂ����s���ł���B����������@�ł̕\���͂�����߂Ă̂��ƂȂ̂����A���Y�ƊE�̂��Ƃ����̖{�ł͐��Y�Ƃ����ϓ_�����ł͂Ȃ����[�������x���̂��Ƃ܂Ŋ܂߂āA����قnj����ɕ��͂��������͉ߋ��ɓǂ��Ƃ͂Ȃ��A�ǎ҂̊F����ɂ��̃|�C���g��v�ē`�������Ƃ̎v�����炱�̌`�ɂȂ����̂ł���B
�������A����͒P�Ȃ�v��ł����Ȃ��̂�����A�����ł��������N�����Ȃ璼���ɖ{������֒��s���čw�����Ăق������A�����_�c���m�����������Ă�����u���{���Ƃ̐^���v�i�����ܐV���j�������ɍw������邱�Ƃ������߂���B
2017�N�̔N���ɂ������āA�F������������Ă����鐅�Y�W�e���ɂ����āA���ꂩ���̋��ɊW����d���̂��Ƃ������[���l���Ă݂�ɂ́A���̖{�͐�D�̋@���^���Ă����̂ł͂Ȃ����Ǝv����B
���̖{�ɐG��邱�Ƃ���̌_�@�ƂȂ��āA2017�N�̓��{�̐��Y�ƊE�������ǂ������֏����ł��Ȃ��Ă����Ă����Ǝv�����̂ł���B
���Y�R���T���^���g�����Ɉ�x�X�V���Ă������̃z�[���y�[�W�ւ�
���ӌ��₲�A���́@info@fish food times
�X�V�����@����29�N 1��1��