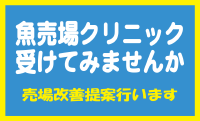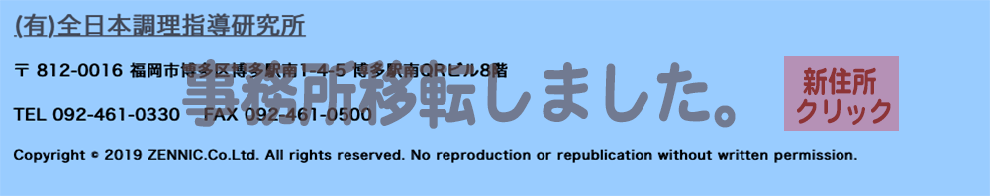�悤���� FISH FOOD TIMES ��
�N���R���T���^���g�������X�V���鋛�̒m���ƋZ�p�̃z�[���y�[�W
�ߘa 7�N 4�����@�� 256
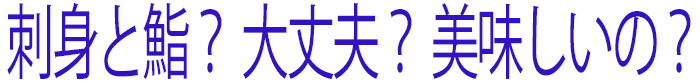

�~�Y�J���C
�~�Y�J���C�Ƃ́E�E�E
�d��367g����412g�̑傫���̃~�Y�J���C��3���w�������B�����̓X�ŐӔC�҂̕���1��400�~�ɂ��Ă��ꂽ�̂ŁAkg�����艿�i��1,000�~�قǂ��ƌ��ėǂ��Ǝv����B

���̋��̕W���a���̓��V�K���C�Ƃ������Ƃ炵�����A���������M�҂͂��̖��̂ɐ̂������݂��Ȃ��B�܂����̖��O�̕t�������u���H�����ꂽ�t���ς̂悤�Ȍ`��̃J���C�v�Ƃ����̂����܂�C�ɂ���Ȃ��̂ŁA��ʋ����Ƃ��Ēʗp����~�Y�J���C�ŁA�������͒ʂ��Ă��������Ǝv���B
�ʖ��~�Y�J���C�Ƃ��������́A���̐g�̓����������ۂ����Ƃ��炫���悤�ŁA�h�g��齂Ȃǂɂ͂��Ȃ��̂����ʂł���A��ʓI�ɂ͉��i�I�ȈӖ��ŕK�����������]���͓����Ă��Ȃ����ł���B
����w�������~�Y�J���C�͂ǂ�����̏�ʕ����ۂ�����オ��A�������O�����炻�̑��݂��n�b�L������قǐ������Ă��āA�܂��ɏ{�̐^�������ɂ���̂��m�F�ł����Ԃ������B

�~�Y�J���C�𗠕Ԃ��ĉ��ʕ�������Ɛ^�����ȐF������ۂ��Ă���A���̕\�ʂ͕\���Ƃ��Ƀ^�b�v���̃k�����ŕ����A�G���̐F���Ԃ��ėǂ��F���c���Ă��āA�N�x�͏�X���Ɣ��f�����B
�M�҂͂ӂƁu�~�Y�J���C�̎h�g��齂͂ǂ�Ȗ�������̂��낤�v�Ǝv�����B�����ŁA�~�Y�J���C������ł���������̕��Ɂu�~�Y�J���C�̎h�g�͔��������Ǝv���܂����H�v�ƕ����Ă݂��B����ƁA���̕Ԏ��́u�����Ă��ӔC�����܂��E�E�E�v�Ə��Ȃ��瓚���Ă��ꂽ�̂������B
����͂������낤�A���̂悤�Ȕ����Ƃ����̂͌���Αz����̂��Ƃł���A�M�Ҏ��g�ł������N���ɂ���������������ꂽ��A�����悤�ȕԓ������邩������Ȃ�����ł���B
���Y�ƊE�ɒ����ւ��A�N����d�˂Ă��������Ȃǖk����B�̒n��ɏZ�ސ��Y�W�҂ɂƂ��āA�~�Y�J���C�̐̂���̃C���[�W�Ƃ����̂́u�Ȑ���������́v�ƃC�R�[���ł���A�Ȑ����̂��h�g�ɂ���Ƃ������z�ɂ͊�{�I�ɂȂ���Ȃ�����ł���B
�́A�M�҂������s�ɂ��钷�l���s��ɖ����ʂ��Ă���1970�N��̍��A�Ȑ�������ԋ��͋��ƂƂ��Ă܂��܂�����Ȏ���ł���A����͒�3���̈�ԋ���Ƃ��ł͂Ȃ��A6����7���ȂǏ����x�߂̎��ԂɁA���s��̊ݕǂɉ��t�����ꂽ�Ȑ�������D����̐��g�����i��M�҂͂悭���Ă������̂ł���B���g������鋛�͂܂��Ɏ�X�G�����̂��̂ł���A���̂Ȃ��ɂ̓~�Y�J���C�����łȂ��A�挎���ō̂肠�����A�J���c����R�_�C�A�A���R�E�ȂǁA�{���ɐF�X�ȋ����������Đ��g������Ă����B
���̎���́A�܂������ʂ̍l�����x�z���Ă������ł���A�ؐ��̃g�����ɂ͊�̖�15kg�𖾂炩�ɒ����������R����ɓ�����Ă����B�����āA���̃g�������R�i2�i��3�i�ł͂Ȃ��A�܂��ɎR�j�̂悤�ɐςݏグ���A�̋���l�����̎R�̏�ɓo���āA�ቺ�ɑ吨���ނ낵�Ă���n��������o�ג������̐l�����������낵�A�吺�Łu ���T�Q���I �Q���Q���I �K�^�{�[�I�v�ȂǂƂ������ƊE�B�������ŁA����̂���肵�Ă����̂��o���Ă���B���Ȃ݂ɁA�������s��Ɋ֘A���鋛�ƊE���Ŏg�p����Ă���ƊE�B���1����10�̐����́A�\�N ������ �e�� ���T �Q���R �K�^ ���V �^�� �L�� �p�C�ł���A���T�Q���Ƃ�450�~�܂���4,500�~�̂��Ƃł���B
�܂�A�Ȑ����̂Ƃ����͍̂��̎���̂悤��1��1����厖�ɑ�Ɉ�����悤�Ȃ��Ƃ͂Ȃ��A�g������15kg�ȏオ�R���肳��A�����X�̎d����ł�1���ł͂Ȃ����P�ʂŎ����������u�y�؋��v�ƌĂ���r�I���������唼�������̂��B������A�p�r�Ƃ��Ă͎h�g�����̋��͏����h�ł���A�唼�����Ă���ϕt�������̋�����ł���A�~�Y�J���C�������������̈�Ƃ��Ċ����Ă������j������̂��B
�������v���N�����Ă݂Ăق����A���⒴�������Ƃ��Ēm��n��A�J���c�ł������A���̓����̓~�Y�J���C�ƈ����͓����ł���A�����̕M�҂��A�J���c���h�g�ŐH�ׂ�Ȃ�Ă��Ƃ͍l�������Ȃ������B�Ȑ���g�����̃A�J���c�͐Ԃ��F�����Ŕ����ۂ��Ȃ��Ă��邾���ł͂Ȃ��A�E���R�͂قƂ�ǂȂ��A���̂͏_�炩�����肪�Ȃ��̂�����A��ʓI�ȑN�x���f��Ō����Ύh�g�ɂ��Ȃ��̂������Ȃ̂ł���B
�����悤�ɁA�~�Y�J���C�����̂̐F�͔����ۂ��A�g�͏_�炩�����肪�Ȃ��A���̏���傩���������яo���Ă��邱�Ƃ��������Ȃ��Ɨ�����A���ʂ͐��ŐH�ׂ悤�Ƃ��Ȃ����낤�B���̂悤�ȃ~�Y�J���C�̃C���[�W�́A���N���Y�ƊE�Ɍg����Ă����l���炷��ƊȒP�ɏ����������̂ł͂Ȃ��A�~�Y�J���C�Ƃ������̈�ۂƂ��Đ[�����ݍ��܂�Ă���͂��Ȃ̂ŁA�~�Y�J���C���h�g���Ă݂����ƌ����Ɓu�����Ă��ӔC�����܂��E�E�E�v�Ə��Ȃ���x�����ꂽ�̂ł���B
�~�Y�J���C�̐��H���i��
����w�������~�Y�J���C�͒��茧�Y�Ƃ������Ƃ����A�ǂ�ȕ��@�ŋ��l���ꂽ���͕s���ł���A�������邵���Ȃ����A���̒��J�Ȉ�������N�x�����炷��ƁA�ߊC�̏��^������ԋ��ɂ����̂ł͂Ȃ����Ǝv�����B
�~�Y�J���C3���̓�1���͓��g���A1���͎ϕt���ɂ��邱�Ƃɂ��Ď��ɂ܂��Ƃ��ȗ����ɂ��邱�Ƃɂ����B�����āA�c��1���̗�������ԏ������đN�x���ǂ��Ɗ�����~�Y�J���C���h�g��齂ɂ��邱�Ƃɂ����B�����H�ׂ�͎̂����ł��蔄�蕨�ɂ���̂ł͂Ȃ��̂�����A�������u�����v�̂��o�傷��Ηǂ��̂��B�Ƃɂ����l�����o���A�~�Y�J���C���h�g��齂�H�ׂĂ݂邱�Ƃɂ����B
�܂��́A�~�Y�J���C���h�g��齂ɂ��邽�߂̎O�����낵�Ɣ�����܂ł̍�ƍH���ł���B
| �~�Y�J���C�̎h�g�E齗p�O�����낵 | |
|---|---|
 |
 |
| 1�C�~�Y�J���C�͕��������������A���������ɂ��Ēu���A�o�n��̐�����E������Ɍ�����B | 8�C�L�ᑤ�̔��r���߂���藣���B |
 |
 |
| 2�C���l�̂��闑���������Ȃ��p�x�ŏo�n�������A������藣����������������B | 9�C���ᑤ�̔w�r���ۂɁA�t���Ő��������B |
 |
 |
| 3�C���o���̌��������ɕ�̐���Ő�������A������������B | 10�C�t���̂܂܁A�w�r���ۂ����ւƐ�i�߂�B |
 |
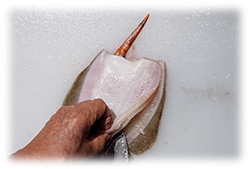 |
| 4�C�L�ᑤ�̕��r���ۂ��J���B | 11�C���ᑤ�̕��r���ۂ̐������A�R�����̕��ւƐ�i�߂�B |
 |
 |
| 5�C���l�̂��闑�����w�ŋ��̂��番������B | 12�C�R�������A�����̕���i�߁A���ᑤ��藣���B |
 |
 |
| 6�C�������ŏ����Ȃ��悤�A�������֎w���g���ĉ������B | 13�C�O���ɂ��낵���~�Y�J���C�̗L�ᑤ����̈ʒu�A���̕������ᑤ�B |
 |
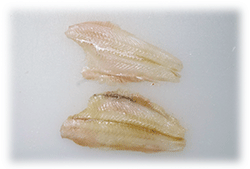 |
| 7�C�������ǂ�������A�R�����̕���i�݁A�Ō�ɗL�ᑤ�̔w�r���ۂ��J���B | 14�C�オ��������������ᑤ�A�����L�ᑤ�B |
�~�Y�J���C�̔�����������Ƃ܂ŏI�������B�����w�g��ƕ��g��ɕ����A�w�g�������g���Ďh�g�A���g�͂ɂ���齂ɂ��邱�Ƃɂ����B
| �~�Y�J���C�̂ɂ���齍�ƍH�� | |
|---|---|
 |
 |
| 1�C����������~�Y�J���C���A�L�ᑤ�A���ᑤ�Ƃ��ɁA�w�g�ƕ��g�ɕ�������B | 3�C�L�ᑤ�̕��g�����̎p���ł�������ɂ���B |
.gif) |
 |
| 2�C�w�g�ƕ��g�ɕ�����ꂽ��ԁB | 4�C���ᑤ�̕��g���E�̎p���ł�������ɂ���B |
 |
|
| �~�Y�J���C�̕��g���g�p�����ɂ����10�J������ | |
| �~�Y�J���C�̎h�g��ƍH�� | |
 |
 |
| 1�C�L�ᑤ�̔w�g���E�̎p���ł�������ɂ���B | 3�C���ׂ��h�g���������肵����A���n�Œ����B |
 |
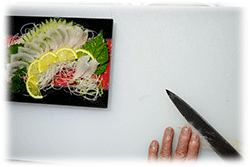 |
| 2�C�L�ᑤ�̔w�g���I���A���ʕ��̔w�g����ĕ��ׂ邽�߂ɁA�������X���C�X��z�u�B | 4�C���ᑤ�̔w�g�����̎p���ł�������ɂ���B |
 |
|
| �~�Y�J���C�̔w�g���g�p����������h�g | |
���̂悤�ɂ��āA�~�Y�J���C�̂ɂ���齂Ɣ�����h�g�����������B���i1�p�b�N�����͋��̌����������J�E���g����Ȃ�A���ꂼ��200�~�Ƃ݂邱�Ƃ��ł���B����ɁA�ɂ���齂̓V������e�킻�̑��̍ޗ�������A�h�g�͑卪�P���A�����炢�A�e���̔�p�������B��Ђɂ���āA���̕ӂ̌����v�Z�ɂ͑��������o�ĈႢ������Ǝv���邪�A���Ԃ���500�~�ȏ�1,000�~�ȉ��̊ԂقǂɂȂ�̂͊ԈႢ�Ȃ��Ɛ�������A�l�����ɂ��Ă͊��}���ׂ��D�����̕��ނƂȂ�͂��ł���B
�����̏��i�͗��v�ʂŗD���ȕ��ނɓ���Ǝv���邪�A���Ă��āE�E�E���̖��̕��͂ǂ��Ȃ̂��E�E�E�A�ǎ҂̊F����͂��̂��Ƃ���ԋC�ɂȂ�Ƃ���ł͂Ȃ����낤���B
�܂��A���_����L�����B����́u���������v�̂ł���B���̐H���͊m���ɏ_�炩�����A�����ۂ����Ɩ����A�����ۂ��ƌ����邩������Ȃ��B�ł���������r�I�������ƌ����A�A�J�A�}�_�C�����������A�C�g�����A�����R�_�C�A�J�}�X�Ȃǂ����l�ɐ��C�̑����g���ł���B�ł́A���������������͕s�����̂��ƌ����A�t�Ɏ|�����Ȃ̂ł���B�܂�A�~�Y�J���C�̂��̒��x�̎����ۂ��Ƃ����̂́A�������Ď|�݂𑝂����ʂ̕����傫���ƌ����邾�낤�B
�����āA���ƌ����Ă��M�҂͐H��ɕ������Ƃ��Ȃ������̂��B�~�Y�J���C�̑N�x�Ƃ����̂��A�̂̈Ȑ�������ԋ��̎��ォ��A����ߊC�̏��^������ԋ�����̂ƂȂ��āA���炩�ɋ��̈�������N�x�Ǘ��̕��@���i�����Ă���悤�ł���B�����̃~�Y�J���C�͎h�g�Ȃǂ̐��H�ɂ͂��Ȃ����̂Ƃ����A�ςɌ��߂��I�ȕΌ��͎����Ȃ������ǂ��̂ł͂Ȃ����Ǝv����B
�����͕s���R�Ȍ`�Ŕ�剻���A�R�e�R�e�Ɏ��������{�B�������Ă͂₳��Ă���B�������~�Y�J���C�̂悤�ɁA�����ł͂Ȃ��_�炩��������A���b�������Ȃ��A�b�T�����ŁA���������ۂ����������邯��ǁA���ɔ���������������̂��B�������������A�������̓V�R���̒��̈�̖��Ƃ��ďܖ����ׂ��Ȃ̂ł���B
�~�Y�J���C�̎ϕt���p�ؐg�Ǝϋ�
�~�Y�J���C�̐��H�������������Ƃ͂������Ď����̐�ŏؖ����ꂽ���A��͂荡���{�̎q�����~�Y�J���C������A�ϋ��Ɠ��g���Ƃ�����ԗ����͊O���Ȃ����낤�B������Ń~�Y�J���C��̔����邱�Ƃ�z�肵�A�ȉ��ɐ悸�ϋ��p�ؐg�̏��i����������A���̎��Ɏϋ��̍�ƍH�����L�����Ƃɂ��悤�B
| �~�Y�J���C�̐ؐg��ƍH�� | |
|---|---|
 |
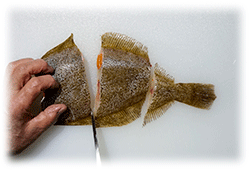 |
| 1�C�������������A������������A���C��@����������Ԃ̃~�Y�J���C�B | 3�C���������������Ƃłقڎl�p�`�ɂȂ������̂��A�����悤�ȑ傫���̐ؐg�ɐ蕪����B |
 |
 |
| 2�C�����������Ɍ����A��ɕ�������ړI�Ŕ�������藎�Ƃ��A�c��̕��ʂ̌`�𐮂���B | 4�C�~�Y�J���C�ň�ԉ��l�����闑����ڗ�������ړI�ŁA����I�ɐ藣���B |
 |
|
| �Ԃ��F�̗��������������~�Y�J���C�̐ؐg | |
����w�������~�Y�J���C�͗������傫���Ȃ����{�̎q����������A��������q�l�ɂ�������ƃA�s�[������ׂ��ł���B���̂��߂ɂ́A�����ʓ|�ł������̏���Ă������������āu����Ȃɑ傫�ȋ���������Ă��܂��v�ƁA���̉��l��\�����Ăق����B
���́A���̃~�Y�J���C�̐ؐg���g�����ϋ��ł���B�q�����J���C�̎ϋ��͋������̒��ł���Ԓ��̒�ԂƎv����̂ŁA�ȉ��̍�ƍH���͕K�������K�v�ł͂Ȃ��̂�������Ȃ����A��ԂƂ��ĊO�����Ɍf�ڂ��Ă��������B
| �~�Y�J���C�̎ϋ���ƍH�� |
|---|
 |
| 1�C���������Ϗ`�Ƀ~�Y�J���C�̐ؐg�����A���ʂŐؐg�̕\�ʂɎϏ`�������Ȃ���A���ՂȂ��������݂��ނ悤�ɂ���B |
 |
| 2�C��̏ォ�����̃A���~�z�C�����Ƃ��W�������A�Ϗ`�̏�����h���Ȃ���Ϗグ��B |
 |
| ��Ɏc�����Ϗ`���X�Ɏς߂āA�d�グ�ɐؐg�̏ォ�炩���ďƂ���o���B |
 |
| �{�C�������{�̐����J����Y���āA�G�ߓI�Ȃ����炢�ɂ���B |
�~�Y�J���C�̉��l�����߂�ЊJ���p�g��
��Ԃ̎ϋ��̎��͗g�����ł���B�g���闿����ړI�Ƃ�����O���ɁA���l����t�����A�������������Ĕ��邱�Ƃ͂���قNJȒP�Ȃ��Ƃł͂Ȃ��B�����A���̓~�Y�J���C�����łȂ��A�J���C�ނ̂قƂ�ǂɊ��p�o����t�����l�Z�@������B����́A�ȉ��́u�ЊJ���p�g���p�v�̏��i�ł���B
| �~�Y�J���C�̕ЊJ���p���i�����H�� | |
|---|---|
 |
 |
| 1�C3���̓��̍ŏ��T�C�Y�����A����ł�367��������A1���̂܂܂̎p�g���ɂ͑傫�������B | 5�C�����̉��ɏ����Ȑ�������A��̐�[�̕��œ����������o���B |
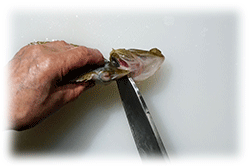 |
 |
| 2�C�E���R������������A�G�������B | 6�C���o����������A���C��@������A�̎R�����ɂ����āA�c�ɐ荞�݂�����B |
 |
 |
| 3�C��̐���̗��ŃG���������������A���̂��番������B | 7�C�c�̐荞�݂���A�w�r�����Ɍ����āA�����̏���i�݁A�G���K���̎�O�Ő�~�߂�B |
 |
 |
| 4�C���̂��������A�G����藣���B | 8�C��ʕ��̔w�g���J������ԁB |
 |
|
| ��J�����������̂��鋛������������`�Ő�������A�~�Y�J���C�̕ЊJ���p�g���p���i | |
���̕ЊJ���̎p�ɂ����~�Y�J���C�����āA�ǎ҂̊F����͂ǂ̂悤�Ɋ������邾�낤���B�M�҂Ƃ��ẮA���̕��@�͊J���������̕����ɓ�����������A�~�Y�J���C�̔�̍����ۂ��\�ʂ����������Ă���ꍇ���A���̕����ԈႢ�Ȃ��N�x���ǂ�������Ǝv���Ă���B�Ⓚ�J���C�ł���������Ȃ��̂͂قڕs�\�ł���A�����Ⓚ�J���C�œ����悤�Ȍ`���o�����Ƃ��Ă��A�ϐF��h���b�v�Ō����ڂ��������蕨�ɂȂ�Ȃ����낤�Ǝv����B
���̕ЊJ���p�̃~�Y�J���C���p�g���ɂ���ƁA�ȉ��̂悤�ɂȂ�B
| �~�Y�J���C�̂����p�g�� | |
|---|---|
 |
 |
| 1�C�~�Y�J���C�S�̂Ɏ�傳���P�������A�������Ԃ�u���A�]���Ȑ��������A���R�V���E�����āA���������܂Ԃ��B | 4�C���悭�F�Â��Ďp�g���������B |
 |
 |
| 2�C180���̖��ɓ���ėg����B | 5�C�ʂ̓�ŁA�l�Q�A�s�[�}���A�^�}�l�M�̐��A����у����V���������u�߂�B |
 |
 |
| 3�C��8���قǂ���ƁA�~�Y�J���C���ꂩ���֕����オ���Ă��āA���ʂ��ďo���オ��B | 6�C�|�A�ݖ��A�����ō�����Ð|���u�߂���ɓ���A���������琅�n���ЌI������������A�Ð|������d�グ��B |
 |
|
| �~�Y�J���C�̎p�g���ɁA�d�オ�����Ð|����������Ċ����B | |
�o���オ�����u�~�Y�J���C�̂����p�g���v�͗�߂Ă����ɔ������������B���̗����͊Ð|�����Ȃ̂ŁA���ǍŌ�ɂ͕ЊJ���ɂ����p�̓������B��Ă��܂�����ǁA���ۂɐH�ׂ鎞�͂��̌`�̂��A�ł���������₷���ĐH�ׂ₷���̂ł���B�܂��A�����Ð|����̖����o����肷���銴�͂��邯��ǁA�S�̃o�����X�Ƃ��Ď��ɔ��������������d�オ�����Ɗ������B
�J���C�Ƃ���������
���āA�������̓~�Y�J���C�ɂ��ċL���Ă������A���낻����߂�����ɂ������Ǝv���B�~�Y�J���C�͓T�^�I�ȑy�؋��Ƃ��Ċ������O���ł��邪�A���̃~�Y�J���C�ȊO�ɂ��A�J���C�Ɩ��̕t�����͓��{�ł�30��ȏ�A���E�ł�100��ދ߂����m�F����Ă���Ƃ̂��Ƃ��B�������A�M�҂͎��ۂ̂Ƃ���A���̃J���C�̂��Ƃɂ��āA���܂�ڂ�������قǂ̒m���͎������킹�Ă��Ȃ����Ƃ��������Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�Ȃ��Ȃ�A�J���C�ނ͂��܂�ɂ���ނ������A�������ǂ����Ă���J���C���m���ǂ��łǂ���������̂��A�����������Ă���J���C�̒m�����W�߂Ă��A�F�X�ƍ������ċ�ʂł��Ȃ����Ƃ��悭���邩��ł���B
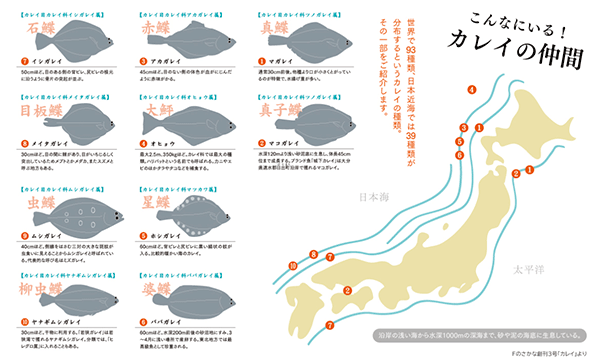
�J���C�ނ̓q�����Ƃ͈���āA�قƂ�ǂ̎�ނ��{�B������Ă��Ȃ��B���̗��R�́A�J���C�ނ͔��ɒ����������鋛���Ƃ������ƂŁA�������������������ƂĂ��x������ł���B���̂��߃J���C�ނ�{�B����ƁA�o�׃T�C�Y�ɂȂ�܂łɁA�G�T���ԓ��^���Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ŁA�{�B�̌����������A�{�B�̑Ώۋ��Ƃ��Ă͂��܂�����Ă��Ȃ��̂ł���B
�A����O�͂���B�s�ꉿ�l�̍����}�c�J���J���C�Ƃ�����ނ́A���ɖk�C����X�Ȃǂŗ{�B�����{����Ă���炵���B�}�c�J���J���C�́A���X�̏ꍇ�͑̒�80cm�̏d6kg�ɂȂ�̂����āA���{�̖k�����݂ȂǂɎ�ɐ������Ă���B�w�r���ƐK�r���ɍ����ȏ�̖䂪����A�E���R���傫���U���U���ŁA���̎���̂悤�Ȃ̂ŁA���̖��̂�����ꂽ�悤�ł���B���̋������g���������Ă��āA�k�C���ł͂�����Ȑ��C��Ń}�c�J�������v��ɉ����Ď�c�������ɂ����g��ł���Ƃ̂��Ƃ��B
�ȉ��̉摜�͖k�C�����A�̃z�[���y�[�W�Ɍf�ڂ���Ă����A�Ϗ��q�Y�̗{�B���Y�}�c�J���J���C�̉��Ձi�������傤�j�Ƃ����u�����h���ł���B

�k�C�����A�̃z�[���y�[�W�ł́A1��700���قǂ̑傫����5,000�~�قǂŔ̔�����Ă��āA���̉��i�͂܂��ɒ��������̕��ނł���B
�������̓}�c�J���J���C���e�[�}�ł͂Ȃ��A�~�Y�J���C�̂��Ƃ��L���Ă������A���̓�̃J���C���r���Ă݂�ƁA�ǂ����낤�E�E�E�B��400g�̃~�Y�J���C�̍w�����i��1��400�~�������̂ŁA���̃R�X�g�p�t�H�[�}���X���ǂꂾ���D��Ă��邩�A��ڗđR�ł͂Ȃ����Ǝv���B�����⍂��齓X�Ȃǂ́A�}�c�J���J���C���d����邱�Ƃ��������Ȃ��Ǝv�����A���Y�����X�܂�1��700���̋���5,000�~�x�����Ƃ����d����s���͊ȒP�ɏo���邱�Ƃł͂Ȃ��B
�܂�A�Ō�ɕM�҂����������������B����̓~�Y�J���C�̂悤�ɑy�؋��Ƃ��Ẵ��b�e����\���A���������Ă��鋛�ł��A���l���ꂽ�����牵���肳���i�K�܂ł̏������@��A�����X���d����Ă���̔�����܂łɂǂꂾ�����J�Ȏ�舵�����������ȂǁA����Ȃ�Ɏ����̖ڂŌ��ɂ߂邱�Ƃ��o����A�\�z�O�̖����𖡂키���Ƃ��o����Ƃ������Ƃł���B
�����ɂ����Ă��������Ǝv�����A��͂蕨���ɑ��Ă͌Œ�ϔO�I�ȕΌ��Ƃ����͔̂����������̂ł���B
���Y�R���T���^���g����m�N�����Ɉ�x�X�V���Ă���
���̃z�[���y�[�W�ւ̂��ӌ��₲�A���́@info@fish food times
�X�V�����@�ߘa 7�N 4�� 1��