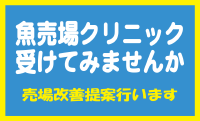�悤���� FISH FOOD TIMES ��
�N���R���T���^���g�������X�V���鋛�̒m���ƋZ�p�̃z�[���y�[�W
����28�N 4�����@��148-2
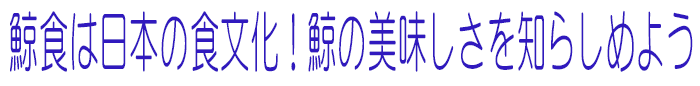

�~���N�~�Ԑg�̎h�g&�ɂ����
�N�W���͑S�g�̂ق�30�`40�����Ԑg�ł���A���̐g�͋ؓ����������܂��Čł����N�W�������A��r�I�_�炩���g�������q�Q�N�W���̕������������Ƃ������Ƃł���A���ł��~���N�N�W���̓q�Q�N�W���̒��ł͍ō��ɔ��������Ƃ���Ă���B
���̃~���N�N�W���̐Ԑg11kg�̓h�`���ƂЂƉ��̌`�œ��ׂ��A������ȉ��̂悤�ȍH���ŏ��i�����Ă������B
| �~���N�N�W���Ԑg�̍����Ǝh�g�H�� | |
|---|---|
 |
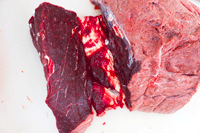 |
| 1�A�X��������o�����܂܂̐Ԑg�u���b�N | 5�A�X�ɓ�ڂ̋ɉ����ē�ɕ����A������ |
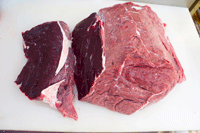 |
 |
| 2�A�傫�ȋɉ����ĕ�����A��ɕ������� | 6�A����30�p�O��A���͂W�p�キ�炢�Ő蕪���� |
 |
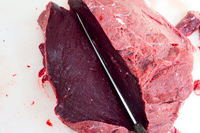 |
| 3�A���������g����؈����̗v�̂ŋ��������� | 7�A�̂Ȃ����ʂ͌����T�p�قǂ̊Ԋu�ɐ蕪���� |
 |
 |
| 4�A30�p���炢�̒����ɍ���肷�� | 8�A��ɂȂ������ʂ�Z����ɐ蕪���� |
 |
|
| �~���N�N�W���Ԑg�̔�����h�g | |
��ʓI�ɍ����Ŕ̔�����Ă���Ⓚ�Ԑg�N�W�����𓀂������͌������h���b�v�ŔY�܂����̂����ʂ����A���̃h���b�v�̌�����1988�N�Ɍ������ꂽ�ߌ~��D���V�ۂ̗Ⓚ�ݔ��������ŌÂ��ݔ��̂܂܂ł��邱�Ƃ��琶���Ă��邱�Ƃ������A����̂悤�ɑN�x�̗ǂ����N�W���̏ꍇ�̓h���b�v���قƂ�Ǐo�邱�ƂȂ��B
����̐��̃~���N�N�W���Ԑg��Z���ŏ��i������ۂɔp�������̂́A�ꕔ�̋������������邾���������̂ŕ����܂藦�͂ق�95���ȏゾ�ƌ��Ă悭�A���̃~���N�N�W���Ԑg�̎d���ꉿ�i��1,600�~�^kg���������Ƃ���Z�����i�̔�����298�~�^100g�ɐݒ肵�Ĕ̔������B
 �@�@�@�@
�@�@�@�@ �@�@
�@�@
��̍��摜�͂��̎��̔̔������A�E�̉摜�͂���X�[�p�[�̗Ⓚ�R�[�i�[�Ŕ̔�����Ă���Ⓚ�Ԑg�N�W���ł���A���̃A�C�X�����h�Y�i�K�X�N�W���Ԑg�͐^��܂ɓ������480�~�^100g�̔����������Ă����B
�Ⓚ�Ԑg�N�W����̔����Ă����X�͍����X�[�p�[�ł͂Ȃ��A�ǂ��炩�ƌ����Έ�����ł��o���Ă���X�ł���A���̂悤�Ȕ�r�I��������������X�ł��O������A�������Ⓚ�N�W��������Ȃɍ��������ɂ��Ă���̂�����A���̎��������ݓ��{�ɂ����ăN�W�����i�������ɍ������i�̍����i�ɂȂ��Ă���̂����ے��I�ɕ\���Ă���B
���̂悤�ɃN�W���������Ȃ��Ă��܂����v���Ƃ����̂́A1982�N�̍��ەߌ~�ψ���iIWC)�Łu���ƕߌ~�����g���A���i�ꎞ��~�j�v���̑�����AIWC���w�肷��15��ނ̃N�W���ɂ��Ă͏��ƕߌ~���ł��Ȃ��Ȃ�A�����s��ł͓��{�����{���Ă��钲���ߌ~�ŕߊl���ꂽ�͂��ȃN�W���������������ė��ʂ��Ă�����̂𗊂�ɂ��Ă��邩��ł���A�N�W���͂��̌����������Ă���悤�ɓX���ł̔������������߂ɁA������{�l���ő��Ɍ��ɂ��邱�Ƃ̂Ȃ������H�ނ̒��ԓ�������Ă���̂ł���B
�������i���l�b�N�ƂȂ��ē��{�ł����̂Ƃ��날�܂蔄��Ȃ��Ȃ��Ă���N�W�����͍����������������Ă����ꂪ����c�邱�Ƃ�����悤�����ǂ��A���c�@�l���{�~�ތ������͔N��60���~���̕ߌ~��p���܂��Ȃ��Ƃ������R�ŃN�W���̕����������i���������邱�Ƃ͂ł����A�u�N�W���̗��ʗʂ𑝂₵��������lj��i�͉����邱�Ƃ͂ł��Ȃ����A�ƒ�̖����̎�v�H�ނƂ��ė��p�𑣐i������̗ʂ͌��X�Ȃ��̂Ŕh��ɏ�����`����킯�ɂ������Ȃ��v�Ƃ������G�ȏɂ���A���Ǐ����X���̉��i�͕����������i��3�{�ɂ͂Ȃ��Ă���ƌ����Ă���B
����M�҂͎������g���������ƌ��ɂ��邱�Ƃ̂Ȃ������N�W�������߂ė����Ƃ��Č������Ă݂悤�ƍl���A�̂��琼�C�ߌ~�̊�n�Ƃ��ėL���Ȓ��茧���ˎs��������K�ˁA�{��̃N�W�����������\����Ɠ����ɐ������̔����فu���̊فv�����w���ăN�W���̌������[�߂邱�Ƃɂ����B
�]�ˎ���̐̂��畽�˔˂̌~�g�ł������������̉v�x�Ƃ́A���C�ߌ~�Ŕ���ȕx�����ƂŗL���ł���A�M�҂͂��̉v�x�Ƃ̃N�W����n���������������ŃN�W��������H����v��������̂����A�N�W���Ɋւ��Ă͑��Ɣ�ׂ悤���Ȃ��قǒ������j�I�Ȑ������̂悤�Ȓn�ł����Ă��A�N�W�������Ƃ����͍̂��╗�O�̓��̂悤�ȑ��݂ƂȂ��Ă���悤�ŁA���̎��ԑтɃN�W�������t���R�[�X��\��̂ɁA�������d�b���Ă���ƂP�������\�邱�Ƃ��ł����Ƃ����̂����Ԃł������B
���Ƃ��\�������Ă��ꂽ�̂͊��B���فu�R���v�ł���A����́u�N�W������܂��v�R�[�X�ň�l4,000�~����Ƃ��������Ĉ����͂Ȃ������������B
| �N�W������܂����� | |
|---|---|
 |
 |
| �Ԑg�Ɣ�̎ϕt�� | �A�I�T����N�W���Ԑg���X�` |
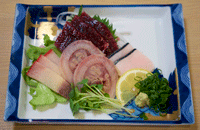 |
 |
| �Ԑg�h�g�E�x�[�R���E�S�q�E���� | �N�W���V���E�}�C |
 |
 |
| �Ԑg�t��ɂ���� | �Ԑg���c�g�� |
 |
|
| ���炵�E�l�X�̃n���n���� | |
�H��̊��z�Ƃ��Ắu�Ȃ��Ȃ��������������v�Ƃ����̂������Ȉӌ��ł���A���s�������ΔN���̍Ȃ͂قƂ�ǂ����߂ĐH�ׂ���̂��肾�����悤�ŁA�N�W�������̖��ɂ��ǂ���ۂ��������悤�Ȃ̂����A���̂��Ƃ͌�������38�N�ɂȂ�v�w�̊ԂŃN�W�����������̊ԂɈ�x���ƒ�ŏo���ꂽ���Ƃ��Ȃ����Ƃ�}�炸�������Ă���A���̎����͕M�҂̉ƒ뎖����ʂȂ��̂Ȃ̂ł͂Ȃ��A��͂葼�̈�ʉƒ�ł���͂蓯���悤�ɃN�W����H�ׂȂ����������ʂɂȂ��Ă���̂��낤�Ǝv����
�N�W�����������\������ɁA�������̔����فu���̊فv���̃R�[�i�[�Łu���Y�Ёv�����y�Y�ɍw���������A����͍��ꌧ�Ďq���Ő��Y����Ă��镓���i�J�u���{�l�j�𔔒Ђ��ɂ����ʋl�ł���A����܂łɉ��x�����y�Y�Ƃ��Ă��������ĐH�������Ƃ�����A���������Ȓ����̕������̃N�W�����������H�ׂ�@����������Ƃ����̂́A�����̂��Ƃł͂��邯��ǂ����ɕςȘb���ƌ��킴��Ȃ��Ɗ������B
 �@�@
�@�@
����M�҂̓~���N�N�W�����������ƂɐG��������߂ăN�W���Ɋւ��邱�Ƃ�����Ȃ�ɕ����Ă݂�ƁA���̂܂܂ł͂��̐���{����u�N�W����H�ׂ�H�����v�������Ă����Ă����������Ȃ��ɂ���Ƃ������Ƃ������邱�ƂɂȂ����B
�n����̐l�������������Ă���Ȃ��ŁA���̐�H���̊m�ۂ͐l�ނ̍ő�̉ۑ�ƂȂ��Ă����ƍl�����A���E�̍����̎�̂ƂȂ�g�E�����R�V�̔N�ԏ���ʂ�75,900���g���i2007�NFAO�����j�ł���A���̓���64��������Ȃǂ̉ƒ{�̉a�ƂȂ��Ē{���̐��Y�ɓ��Ă��Ă���Ƃ������Ƃł���A2007�N�ɒ{�����Y�ʂ�9,600���g���������̂�2019�N�ɂ�1��1,900���g���ɒB����ƌ����Ă��āA�����Ē{���̐��Y�ɂ́u����10�{�̎���������100���{�̐����K�v�v�Ɛ�������Ă���̂��B
�����ۂ��N�W���Ƃ����̂́A�G�T���^�����ɊC�ŕߊl���邾���Ō~���Ƃ��Đl�Ԃ̈ݑ܂������Ƃ��ł��鑶�݂ł���A�������N�W������r�o���ꂽ���A�����R�̃T�C�N���̒��Ɋ҂��Ă����Ƃ������ɕ��ׂ̂Ȃ����R�ɗD�����H���ł���A���̃N�W���͑S���E�̊C�Ƀ~���N�N�W�������ł�76�����A�}�b�R�E�N�W���͉���200��������Ƃ���Ă��č������̐��͂ǂ�ǂ������Ă���̂ł���B
���̃N�W���͌~���Ƃ��Ċ��p�ł���ɂ�������炸�A���E�͏��ƕߌ~�����g���A���ɂ���ĕߊl���~���������Ԃɂ��Ă��邾���ł͂Ȃ��A���͂��̂��Ƃ��������Ȃ̂ł͂Ȃ����݂���ɑ傫�Ȗ��ƂȂ��Ă���̂́A�N�W�����M�����Ȃ��قǑ�ʂ̋���H�ׂĂ��܂��Ƃ��������ł���B
�N�W���͕��ϓI�Ɂu1���ɑ̏d��3�������̋���ނ�H�ׂ�v�Ƃ������Ƃł���A�N�ԂɊ��Z����Ƒ̏d��10�{���̋���ނ�ߐH���Ă���Ƃ����v�Z�ɂȂ�A���̕ߐH�ʂ��N�W���S�̂ɏd�ˍ��킹�Ă݂�ƂQ��4,000���g������T���g���ƂȂ�A���ݐl�Ԃ��P�N�ԂŐ��E���̊C�ŋ��l���Ă��鋛�̗ʂ�9,000���g���ł��邩��A�N�W���͐��E�̐l�Ԃ��H���Ă��鋛�̗ʂ̂R�`�T�{�̓V�R�̋���H�ׂĂ���Ƃ����v�Z�ɂȂ�̂ł���B
�����Ă���܂ł̏펯�Ƃ��ẮA�q�Q�N�W���̒��Ԃ̓v�����N�g����I�L�A�~�Ȃǂ̊C�m��������������H�ׂĂ���ƍl�����Ă����̂����A����͓�X�m�����Ɍ����Ă̂��Ƃł����Ėk���吼�m�ŕߊl���ꂽ�~���N�N�W���݂̈̒�����́A�ȉ��̉摜�ɂ���悤�ɑ�ʂ̃T���}�A�C�J�A�T�o�A�X�P�g�E�_���Ȃǂ��o�Ă��āA�l�Ԃ��H�ׂĂ���̂Ɠ��������ʂɕߐH���Ă��邱�Ƃ����������̂ł���B
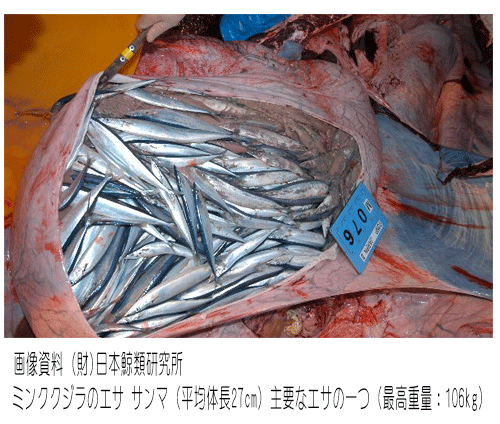
�l�Ԃ̉ߏ�ȕی�ƂȂ��Ă���u���ƕߌ~�����g���A���v�ɂ���ĊC�m���Ԍn�̃o�����X���������悤�ł���A�f�[�^������ׂ�ƃN�W���ނ��������Ă��������ƊC�m�����̋��l�����̎����Ƃ͂قڈ�v���Ă���Ƃ������Ƃł���A���̂܂܃N�W���̑�������u�����܂܂ɂ��Ă����Ɓu�l�ԂƃN�W���̋��̑��D��v�ɐl�Ԃ������āA���̐�H�ׂ鋛���傫���������Ă��܂����Ԃ��l�����Ȃ����Ƃ͂Ȃ��̂ł���B
���݃~���N�N�W���͐��E���̊C��76�����ȏ㐶�����A�قڔN��4�����x�ő������Ă��邱�Ƃ��痝�_��ł�1�N��15,000����ߊl���Ă����Ȃ��ƌ����Ă���A����M�҂̃N�W���̕��ɂ����Ď����Ƃ��ĐF�X�ƎQ�l�ɂ����Ă��������������u���{�̌~�H�����v���ꂽ�������V���ɂ��ƁA�u�~���N�N�W����N��4,000���i2���g���̌~�����Y���\�j�̎����\�ȏ��ƕߌ~���ĊJ���ׂ��v�Ǝ咣����Ă���B
�M�҂͏������V���̖{���瑽���̂��Ƃ��w�Ԃ��Ƃ��o�����̂����A�u���{�̌~�H�����v�ɋL����Ă���ȉ��̕��͕͂M�҂������Ȃ�ɉ��߂��ĕʂ̕\���ŋL�q��������A�������̕��͂����̂܂܋L�ڂ���̂��K���Ǝv�����̂ňȉ��ɂ�������̂܂ܓ]�ڂ������Ă����������Ƃɂ���B
�u���Ӕj�]����{���H�����v�F �������V�� �l�Ԃ̖O���Ȃ��~���������߂ɁA�g���𑱂����Ȃ��Ȃ�������Ӓ{�Y�ƊE�ɂ���������ł��낤�B�E�V��BSE�A�u�^�͓̌����u��g���R�����A�g���͒��C���t���G���U�ȂǁA�u���v��H�ׂ�Ƃ������Ƃɂ͂��ꂱ���d��Ȗ�肪��������Ă���B�����ɂ��̖��̈����[���ł���A�����ɂ͋]���ƕ��S���������邱�ƂɂȂ�B ���Ƃ��A���炵�Ă��铮���̊����ǂ�h�����߂ɖc��ȃR�X�g�S���Ȃ���Ȃ�Ȃ����A���������ǂ����������܂������Ԃɔ�щ��Đ��\�����P�ʂŎE�������Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ȃ�B����ɂ͂��̌�̍Č������]��Q�𒆐S�Ƃ��āA���̂ɂ��ނ悤�ȓw�͂���������B���{�I�Ɂu���v�̏�ʼn����̎���𑱂��Ă������߂ɂ́A�L�`���`�̔�p��������Ƃ������ƂȂ̂��B ���ӁA���E�̒{���s�ꂪ�s���Â܂�A���̕⊮��V�R�̐H���ł���~�����S�����オ����Ă���B�킽�����g�A�����̒{�Y�_�ƂƂ̏o��ɂ��b�܂�邱�Ƃ������A�؎��ɂ��̋ƊE�̔��W���肤���炱���A�����{�Y�Ƃ��������I�ȍ\�����P��}�邱�Ƃ��d�v�ł���Ƃ��l����B�������A�~���␅�Y�����ʂ����^���p�N�������Ƃ��������́A�܂��܂��傫���Ȃ����ƌ��킴��Ȃ��B |
|---|
���̂悤�ɏ������͋L����Ă��邪�A���̕��͔͂��ɍl����������[�����@������B
���E�����ƁA���Ƃ��s�𗝂Ȃ��Ƃ�����U���Ă܂���ʂ邱�Ƃ������Ē��������Ƃł͂Ȃ�����ǁA�N�W���Ɋւ���u���ƕߌ~�����g���A���v�����̍ł�����̂̈�ł͂Ȃ����ƍl����B
�ȑO FISH FOOD TIMES �ł́A No.85�u�N�W���E���g�����蔫����v�i����23�N1�����j �̒��ŁA�ʂ̊ϓ_����N�W���̂��Ƃ��L�q���Ă����̂œǎ҂̊F����͂����������`���Ăق������A�����ɂ��L���Ă���悤�ɐ̌~������邽�߂����ɃN�W�����E���Ă������ď������A���x�́u�N�W�����E���͉̂��z�v�Ƃ�������_�œ��{�̕ߌ~���֎~������Ƃ����u�s�𗝂Ș_���̔��v�ɂ͂ƂĂ����Ă�������̂ł͂Ȃ��B
��������������_�������܂ł������ʂ���������͂��͂Ȃ��A���������q�ׂ��Ă���悤�ɐ��E�������͗���̐��������ł͉����ł��Ȃ��قǂ̐H����@�������Ă���ƁA�S��������_���̓W�J�Ŏ��������̐��������咣���A�l�ނ̐H�����Ƃ��ăN�W����ߊl������Ȃ��悤�ɂȂ�̂ł͂Ȃ����Ǝv����B
���̎������ɂȂ�̂�������Ȃ����A���̎��̂��߂ɂ����{�͗��j����N�W���̐H�������₳�Ȃ��悤�ɂ��Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ��ƍl����B
���ݓ��{�ɂ����ăN�W���𒿖��Ƃ��č����i��������悤�ȍ��̗���͕ς��Ă����ׂ��ł���A���̂��߂ɂ͗��s�s�Ș_����U����ď����̃��K�}�}��ق��ĕ��������ł͂Ȃ��A���{�͗��j����N�W���̐H�������������邽�߂ɂ����ƕߌ~�̕�������������悤�w�͂��Ă����ׂ��ł���B
| �O�y�[�W�֖߂� |
|---|
���Y�R���T���^���g�����Ɉ�x�X�V���Ă������̃z�[���y�[�W�ւ�
���ӌ��₲�A���́@info@fish food times
�X�V�����@����28�N 4��1��